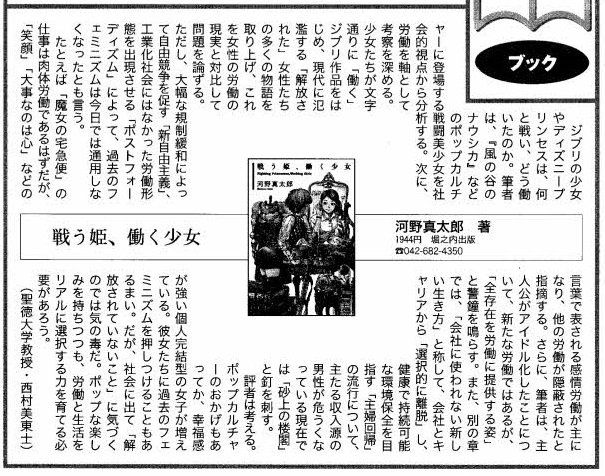書評
評者は考える。格差拡大、不安、不透明な社会であるにもかかわらず、若者の幸福感の高まりと性差別に関する保守化が進行していることには、このようなメディアの影響もあるのだろう。次に、彼らの気持ちを共感的に理解しつつも、現実社会に適合した考え方、生き方、働き方を提起し、創造できるような働きかけを考えたい。不安、不透明の中でも、自由を尊び、納得がいく自己決定ができるようにすること、そのための新しい価値の創造が求められている。
ポップカルチャーのおかげだろうか、「とても幸せ」と答える若者が増えている。これは伸ばしてあげたい。だが、大人になって「こんなはずではなかった」となるのでは気の毒だ。夢をもちつつも、自己と社会のリアルな認識と位置づけのもとに労働と生活を選択する力を育てたい。
少女たちが文字通りに「働く」ジブリ作品はもちろんのこと、現代に氾濫する「解放された女性」たちの物語と、新自由主義のもとでの女性的労働や女性化された労働の世界を批判的に論ずる。大幅な規制緩和によって自由競争を促す「新自由主義」、工業化社会の次の労働が、過去のフェミニズムを困難にしていると言う。
たとえば「魔女の宅急便」は、肉体労働であるはずだが、「大事なのは心」「笑顔でいること」などの言葉で表される感情労働が主になり、他の労働が隠蔽されていると言う。さらに、筆者は、主人公がアイドル化したことについて、新たな労働の姿としつつ、「全存在を労働に提供」するものとして批判する。
また、別の章では、「会社に使われない新しい生き方」と称して、会社とキャリアから「選択的に離脱」し、健康で持続可能な環境保全を目指す「主婦回帰」の流行について、主たる収入源の男性が危うくなっている現在では「砂上の楼閣」と釘を刺す。
書評
河野 真太郎
戦う姫、働く少女
発行:堀之内出版
2017年7月20日
価格 1,944円
この本のテーマは「ジブリの少女やディズニープリンセスは、何と戦い、どう働いたのか」である。まず、戦闘美少女を社会的視点から分析する。『風の谷のナウシカ』から『新世紀エヴァンゲリオン』、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』にいたるまでのポップカルチャーにあふれる「戦う姫・少女」の姿は、いかなる社会の変化や、願望を示しているかを明らかにしようとする。次に、労働を軸としてその考察を深める。少女たちが文字通りに「働く」ジブリ作品はもちろんのこと、現代に氾濫する「解放された女性」たちの物語と、新自由主義のもとでの女性的労働や女性化された労働の世界を批判的に論ずる。大幅な規制緩和によって自由競争を促す「新自由主義」、工業化社会の次の労働が、過去のフェミニズムを困難にしていると言う。
たとえば「魔女の宅急便」は、肉体労働であるはずだが、「大事なのは心」「笑顔でいること」などの言葉で表される感情労働が主になり、他の労働が隠蔽されていると言う。さらに、筆者は、主人公がアイドル化したことについて、新たな労働の姿としつつ、「全存在を労働に提供」するものとして批判する。
また、別の章では、「会社に使われない新しい生き方」と称して、会社とキャリアから「選択的に離脱」し、健康で持続可能な環境保全を目指す「主婦回帰」の流行について、主たる収入源の男性が危うくなっている現在では「砂上の楼閣」と釘を刺す。
評者は考える。まず、同書によって、ポップカルチャーが青少年の意識や労働観に与える影響を考えたい。格差拡大、不安、不透明な社会であるにもかかわらず、若者の幸福感の高まりと性差別に関する保守化が進行していることには、このようなメディアの影響もあるのだろう。次に、彼らの気持ちを共感的に理解しつつも、現実社会に適合した考え方、生き方、働き方を提起し、創造できるような働きかけを考えたい。不安、不透明の中でも、自由を尊び、納得がいく自己決定ができるようにすること、そのための新しい価値の創造が求められている。
ポップカルチャーのおかげだろうか、「とても幸せ」と答える若者が増えている。これは伸ばしてあげたい。だが、大人になって「こんなはずではなかった」となるのでは気の毒だ。夢をもちつつも、自己と社会のリアルな認識と位置づけのもとに労働と生活を選択する力を育てたい。
紹介
ジブリの少女やディズニープリンセスは何と戦い、どう働いたのか。それは現代女性の働きかたを反映していた―。『逃げ恥』から『ナウシカ』まで。現代のポップカルチャーと現代社会を縦横無尽、クリアに論じる新しい文芸批評が誕生!
目次
はじめに
第一章 『アナと雪の女王』におけるポストフェミニズムと労働
革命的フェミニスト・テクストとしての『アナと雪の女王』
二人のポストフェミニストの肖像
トップ・ガールズとブリジットたちの和解?
シェリル・サンドバーグは存在しない――グローバル資本主義とその本源的蓄積
労働なき世界と「愛」の共同体
第二章 無縁な者たちの共同体――『おおかみこどもの雨と雪』と貧困の隠蔽
承認と再分配のジレンマ
『おおかみこどもの雨と雪』と貧困の再生産
ポスト・ビルドゥングスロマンと成長物語の変遷
『ハリー・ポッター』、『わたしを離さないで』と多文化主義
無縁な者たちの共同体
コーダ 現代版『ライ麦畑でつかまえて』としての『僕だけがいない街』
第三章 『千と千尋の神隠し』は第三波フェミニズムの夢を見たか?―アイデンティティの労働からケア労働へ
フェイスブックという労働
『魔女の宅急便』のポストフェミニズム
『千と千尋の神隠し』は第三波フェミニスト・テクストか?
『逃げるは恥だが役に立つ』?─―依存労働の有償化、特区、家事の外注化
第四章 母のいないシャカイのユートピア──『新世紀エヴァンゲリオン』から『インターステラー』へ
スーパー家政婦、あらわる
『インターステラー』の母はなぜすでに死んでいるのか?
『インターステラー』の元ネタは『コンタクト』なのか?
『コンタクト』と新自由主義のシャカイ
セカイ系としての『インターステラー』
『エヴァ』とナウシカのポストフェミニズム
コーダ1 AIの文学史の可能性──『ひるね姫』と『エクス・マキナ』
コーダ2 矛盾の回帰?─―『ゴーン・ガール』と『WOMBS』
第五章 『かぐや姫の物語』、第二の自然、「生きねば」の新自由主義
「生きろ/生きねば」の新自由主義
『風の谷のナウシカ』における自然と技術の脱構築
技術と自然の脱構築と労働の隠蔽
『風の谷のナウシカ』、『寄港地のない船』、(ポスト)冷戦の物語
罪なき罰と箱庭
終章 ポスト新自由主義へ
没落系ポストフェミニストたち
主婦が勝ち組?─―ハウスワイフ2・0から『逃げ恥』へ
セレブ主婦の蜃気楼
貧困女子の奮起
エイミーたちの願いとジンジャーたちの連帯
Fighting Princesses, Working Girls
Contents
Introduction
1 Postfeminism and Labour in Frozen
2 The Community of the Excommunicants: Wolf Children and the Suppression of Poverty
3 Did Spirited Away Dream of Third-Wave Feminism?: From Identity Labour to Care Labour
4 The Utopian ‘Society’ without Mothers: From Neon Genesis Evangelion to Interstellar
5 The Tale of the Princess Kaguya, the Second Nature, and the Neoliberalism of the Injunction to ‘Live’.
Conclusion: Towards Post-Neoliberalism
Works discussed
Introduction
Star Wars: The Force Awakens
Nausicaa of the Valley of the Wind
Chapter 1
Frozen
Bridget Jones’s Diary
Lean In
Top Girls
Snow White and the Seven Dwarves
Mulan
The Princess and the Frog
Chapter 2
Wolf Children
The Catcher in the Rye
The Harry Potter series
Never Let Me Go
Daniel Deronda
Erased
A Silent Voice
Chapter 3
Kiki’s Delivery Service
Spirited Away
The Full-Time Wife Escapist (Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu)
Chapter 4
I Am Mita, Your Housekeeper (Kaseifu no Mita)
Interstellar
The Road
Contact
Doctor X
Neon Genesis Evengelion
Nausicaa of the Valley of the Wind
Gone Girl
Wombs
Chapter 5
The Tale of Princess Kaguya
Nausicaa of the Valley of the Wind
Non-Stop (Starship)
Princess Mononoke
前書きなど
※ 本書では登場する作品の結末も含むあらすじを紹介しています
本書が目指すのは、「戦闘美少女の社会的分析」である。『風の谷のナウシカ』から『新世紀エヴァンゲリオン』、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』にいたるまで、わたしたちのポピュラー・カルチャーは戦う姫・少女の姿であふれている。それらの女性像は、いったいいかなる社会の変化を、そしてどのような願望のありかを指し示しているのか? この疑問に取り組むにあたって軸となるのは労働の問題、それもとりわけ女性の労働/女性と労働という問題だ。少女たちが文字通りに働くジブリ作品はもちろん、現代に氾濫する「解放された女性」たちの物語と、新自由主義とポストフォーディズム下における女性的労働そして女性化された労働の世界との関係はいかなるものなのか? 本書はそうした疑問をさまざまな作品を縦横無尽に接続しながら論じる。そうして可視化された「現在」を、わたしたちが乗り越えていくために。
著者プロフィール
河野 真太郎 (コウノ シンタロウ) (著/文)
(2019年5刷時)
専修大学教授。1974年山口県生まれ、一橋大学大学院商学研究科准教授を経て2019年4月より現職。関心領域はイギリスの文化と社会。著書に『〈田舎と都会〉の系譜学』(ミネルヴァ書房、2013年)、共著に『文化と社会を読む 批評キーワード辞典』、(研究社、2013年)訳書にピーター・バーク『文化のハイブリディティ』(法政大学出版局、2012年)、共訳書にレイモンド・ウィリアムズ『共通文化に向けて―文化研究1』(みすず書房、2013年)など。
(刊行時)
一橋大学大学院商学研究科准教授。1974年山口県生まれ。関心領域はイギリスの文化と社会。著書に『〈田舎と都会〉の系譜学』(ミネルヴァ書房、2013年)、共著に『文化と社会を読む 批評キーワード辞典』、(研究社、2013年)訳書にピーター・バーク『文化のハイブリディティ』(法政大学出版局、2012年)、共訳書にレイモンド・ウィリアムズ『共通文化に向けて―文化研究1』(みすず書房、2013年)など。
若者文化研究所は若者の文化・キャリア・支援を専門とする研究所です。