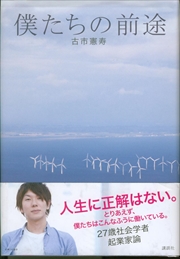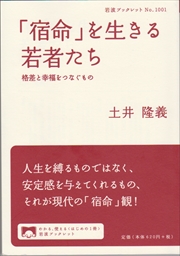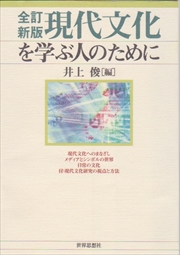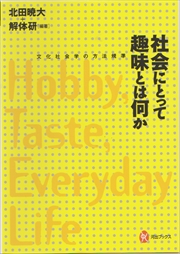�@��ҕ����������@���������m
���ɂ��鐶��������邽�߂�
���Ȍ��肪�����A�ӔC�������ɖ߂��Ă��Ă��܂��l���Љ�B
�l���Љ�͎���̕K�R���B
�]�_�Ƃ́u�l���������Ȃ��v�Ƃ����B
�������A��҂́A���̌l���Љ�̒��Ő����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�l���̂Ȃ��Łu�K���ɐ�����v���@��g�ɂ��悤�Ƃ��Ă���B
�B��̎��Ȃɂ�����炸�A���Ȃ��u�������v���邱�Ƃ��A���̈���B
�������A������ɂ���A�����ł́A���Ȍ���͂�{���K�v������B
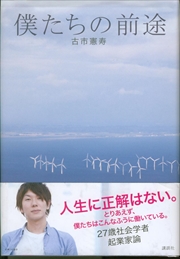
�l�����̑O�r
�@�u����������������ł���v�ƌ�����l���Љ�́u�ċA���v�̒n�����X���[���鐶��������A�u�ċA���v���ė����Ȍ���A���ȐӔC�̐������ɓ]�����邱�Ƃɂ��A�^�̐����Ə[��������B
�@�Љ�I�ɃR���g���[�����ꂽ���Ƃł��A���s����A�l���Љ�ł́A���ǁA�u����������������ł���v�ƌ����Ă��܂��B������ċA���Ƃ��ŁA�ʏ�̘_�҂���͐�]�I�Ȏ������̂悤�Ɏ�舵���Ă���B����ɑ��ČÎs�́A�����ɖҗ�ɗ���������Ȃ����Ƃɂ���āA��҂͐�]���炭���蔲���Ă���ƌ����A
�@���āA����͂ǂ�����悢�̂��B�l���̐i�W�́A��҂ɂƂ��Ď���̕K�R�ł���B���Ƃ�����A���̂Ȃ��ŏ[�����Đ�������悤�A�l�̎Љ�ƌl������̓I�Ɏx�����邱�Ƃɂ���āA�u�قǂقǁv�Ȃǂł͂Ȃ��A�E��A�ƒ�A�Љ�n��̈���Ƃ��ď[���������U�𑗂��悤�x���������B
�@���̖{�ł́A�җ�Ƃ͈�����悷�N�ƉƂ������o�ꂷ��B�Îs���g���Ј��R�l�̂h�s�x���`���[�̈�������A�ׂ����Ă���ꂵ�Ȃ��A�Ј������₳�Ȃ��A�����}���V�����ɏZ�݁A��Ђ̓t�@�~���[�̂悤�ȑ��݂Ƃ����B�����������͋����Ɓu�Ȃ��芴�o�v���ɂ��A�����œ������Ƃ��邢�܂̎�҂�f�i�Ƃ�����B
�@�Îs�́A�N�Ƃ����߂悤�Ƃ��Ȃ��B�ŏI�͋߂��ł́A�u���R�i���Љ�v�Ƃ������t���N����B�r�U�Ȃ��ł������̍��Ɏ��R�ɍs����A�ł��A�A���Ă���Ȃ��Ȃ��Ă��u��������R���v�Ɲ�������B�]�҂̂܂��ɂ��u�߂�ǂ�������C�O���s�͂������Ȃ��v�Ƃ�����҂������Ă���̂�������B����A���R�́A������Ŋ�ׂ邱�Ƃł͂Ȃ��B�N�Ƃ̋K���ɘa�ɑ��Ă����l�Ȃ̂��낤�B
�@�Љ�w�ł́A���l�ɁA�l�̎��R�ȑI���ɐӔC���A������l���̃}�C�i�X�ʂ���������B�������A���Љ�w�҂ł���Îs�́A�u�ǂ����������҂��Ȃ�A�D���Ȑl�ƍD���Ȃ��Ƃ�����Ă������v�A�u�Љ��ς������Ȃ�Ă������ꂽ�C�����͂Ȃ��v�ƌ����B�Љ�ɖҗ�ɗ���������Ȃ����Ƃɂ���āA�ނ́u�l����㩁v���炭���蔲���Ă����Ƃ�����B
�@���āA����ɂ����ẮA�u���R�i���Љ�v�̂Ȃ��A�ǂ̂悤�Ɏ�҂̘J���ς���Ă�̂��B�u�җ�Ɏ��Ȍ���Ő�����v�Ƃ����̂��A����Ƃ��u�����炵�����ɂ��邽�߂ɂ́A�����蔲����v�Ƃ����̂��B�]�҂́A���z�Nj��̋���ɂ����ẮA���̂ǂ���ł��Ȃ��A���N�̌l���̃v���X�̑��ʂ�L���A���������ɂ��Ȃ���A�E���n��ł́A���҂Ɛ����������A�x�������l�ނ��琬���邱�Ƃ��\�ƍl����B
�y�Q�l�z���������m�����֘A�_��
�w���̎��Ȍ���\�͂����߂���ƕ��@
2000�N11�����[�N�V���b�v�^���Ƃ̍\���v�f�Ƃ��̌��ʁ|�w���̎��Ȍ���\�͂����߂���ƕ��@�A�w��w����w��x22��2���App.194-202
�y�v�|�z2���Ԃ́u���U�w�K�T�_�v�̎��ƂŁA�w�����ǂ̂悤�Ɏ��Ȃ⑼�҂ɑ���C�Â����̂��A���̕ϗe�̉ߒ����𖾂��邱�Ƃɂ���āA�w���̎��Ȍ���\�͂����߂���Ƃ̍\���v�f�Ƃ��̌��ʂ𖾂炩�ɂ����B��1�ɁA���[�N�V���b�v�^���Ƃɂ���āA��������Ύ��ցA�Ύ�����Α��҂ւƊw���̋C�Â���������A�Α��҂���ĂёΎ��⑦���̂��[���C�Â��ւƏz����ߒ������炩�ɂȂ����B��2�́A�w���̎��Ȍ���\�͂̓��B�i�K�̔c���Ɋ�Â��헪�I�Ȏw�����e�Ǝ��ƍ\���̕K�v�������炩�ɂȂ����B

NHK���w���E���Z���̐����ƈӎ�����2012�|����ꂽ20�N�����g�K���h�ȏ\��
�u�ƂĂ��K�����v�i���w��55���A���Z��42���j�Ƃ��鐶�k���A����10�N�ʼnߋ��ō��̑��������������B���ւ̃��`�x�[�V���������サ���B�����ŁA�Îs�������́A��Ƃ苳��̐��ʂƕ]�����A�u����ȂɊ肢�ʂ�ɂ����q�Ɉ���Ă���̂ɁA�����Ƃ͋���ɑ��ĉ����������̂��v�Əq�ׂ�B
�����̏\��̍��̎��ƂƎ������v���o���Đ��k�𗝉����悤�Ƃ��邱�Ƃ́A�Ԉ���Ă͂��Ȃ��B�N�����L�̕s�ς̉ۑ�͋��ʂ��Ă��邩��ł���B�����������ɁA���̏\��̕ω������Ă����K�v������B���̒����́A�u�r���w�Z�v���Љ���ɂȂ���82�N����A87�N�A92�N�A02�N�ƍs���Ă����B
�@�u�ƂĂ��K�����v�i���w��55���A���Z��42���j�Ƃ��鐶�k���A����10�N�ʼnߋ��ō��̑��������������B���ւ̃��`�x�[�V���������サ���B�����ŁA�Îs�������́A��Ƃ苳��̐��ʂƕ]�����A�u����ȂɊ肢�ʂ�ɂ����q�Ɉ���Ă���̂ɁA�����Ƃ͋���ɑ��ĉ����������̂��v�Əq�ׂ�B�����ɁA����u����ꂽ20�N�v�̃t���[�^�[�������e����ɂȂ����Ƃ��A���̂悤�ɂ��܂��͂����Ȃ��Ɨ\�z���Ă���B
�@�Îs���́A�u�X�N�[���J�[�X�g�v�̉��ʂɂ����Ă��u���͉��ŗF���������邵�A���������������Ă���v�ƎЉ�w�̗��ꂩ�番�͂���B�������A����w�̗��ꂩ��́A���̂悤�ȁu�K���v�ɑΛ����āA�u�x���I���y�̍K���v�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�u�����q�ł��邾���ł͍K���ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Љ�ɏo�Ă����A�K���Ȑ��U���߂������߂ɂ́A�Љ�̂Ȃ��Ŏ��Ȕ������邽�߂̎���̊m���ƎЉ�ł̈ʒu���߂��x������K�v������B
�@�u�v����\���肽���v���u�܂������Ȃ��v�Ƃ����82�N19������A12�N69���ɂ܂ő��������B�e�ɂ����R�����A�����悢�B80�N��Ɂu�r���w�Z�v�ň�������t�́A���̂悤�ȁu�����h���k�v�̗ǂ������A�������܂Ƃ܂点���Ɉ�Ă邱�Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�����L�[��������{
�u�����Ȍ|�p�v�ɑ���o�b�h�Z���X�A�u�C�����v��u�J�v�Ƃ��������O�̂��ƁA�Ƒ��⒇�Ԃ��ɂ���Ƃ������̗ϗ��ς��Z�������ЂƂ̕����ł���Əq�ׂ�B�R�~���j�P�[�V�������A�����|�l�̂悤�ɒB�҂ŁA���M�������Đ����Ă���B�����āA�u�N�̐S�ɂ������L�[�͂���v�Ƃ��A����́A�����L�[�����̃G�b�Z���X���L���g�U��������ł���A�ނ��뎩�������Č����Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@�����L�[�Ƃ͕č��l�̑��̂ŁA���́A�č��̎�҂̕������܂˂�u�s�ǐ��N�v���w���Ă����B���̂��߁A�ȑO�́A�w�Z���r�炷�u�G�v�������B�������A�v�t���E�N���̐��_�a���w����Ƃ���֓����́A���́u�����L�[�v�ɂ��āA�u�����Ȍ|�p�v�ɑ���o�b�h�Z���X�A�u�C�����v��u�J�v�Ƃ��������O�̂��ƁA�Ƒ��⒇�Ԃ��ɂ���Ƃ������̗ϗ��ς��Z�������ЂƂ̕����ł���Əq�ׂ�B�R�~���j�P�[�V�������A�����|�l�̂悤�ɒB�҂ŁA���M�������Đ����Ă���B�����āA�u�N�̐S�ɂ������L�[�͂���v�Ƃ��A����́A�����L�[�����̃G�b�Z���X���L���g�U��������ł���A�ނ��뎩�������Č����Ȃ��Ȃ��Ă���Ǝw�E����B
�@�Βk�̂Ȃ��ŁA���́A�e�n�̊w�Z�Ŏ��グ���Ă���悳�����\�[�����Ȃǂ̃����L�[���ۂ��ɂӂ�A�܂��A�X�p���^����A�����搶����L�[�搶�A�u�f�s�n�v��u��������v�Ȃǂ̃��f�B�A�ɂ�锽�m����`�̗�����w�E����B�u���������˂Ă��Ă����傤���Ȃ��v�A�u�Ƃɂ����^�S�Ɛ������œ������Ă����ΐl�͕ς��v�A�����āu���_�͔M�̑O�ɔs�ꋎ��v�Ƃ����O���ᔻ����B
�@�������A���́A��s�͂Ƃ����������L�[���͍X��������K�v�͂Ȃ��Ƃ����B�����L�[��˂��l�߂Ă����ƁA�J�⋦�����ɌX���A�܂Ƃ܂������̂ɖ𗧂ƌ����B�����ɁA�u�����v�T�O�ƃZ�b�g�Łu�l��`�v���ăC���X�g�[������悤����B
�@�q�b�v�z�b�v�̗��ɂ͍��l�̗��j������A�悳�����̗��ɂ͂܂��Â��肪����B��ÂƂ��Ă͂Ƃ������A����ɂ����ẮA�Љ�`���҂̈琬�̂��߂̖ڕW�ɉ����āA�u�Ȋw�I�Ȍ����E�l�����v�⎩�ȂƂ̑Θb�̕��@�_��ނ�ɋ��������������B���̂��Ƃɂ���āA�ނ�́A��荪�����鎩�M�������Ƃ��ł��悤�B

�u��ҁv�Ƃ͒N��:�A�C�f���e�B�e�B��30�N
������܂�Ƃ܂Ƃ܂��Ă��܂��̂ł́A�]�܂��������Ƃ͌ĂׂȂ��B��������̌��́u������v�i�����I���ȁj�́A���l�ȏɂ����āA���l�ȉӏ������点�������A���������Ă��������B�܂��A���t�͑��l�ȗF�B�Ɛڂ���Ƃ��́u�����I���ȁv�Ƃ͈قȂ�A�����I�u�[���Ƃ͈قȂ�A�َ��̑��҂Ƃ��Ă̖�����������̂ł��肽���B��������A�u�����I���ȁv���������u�����I���ȁv�̊m�����\�ɂȂ邩������Ȃ��B
�@����͎�҂́u�����T���̗��v���x���i�P�X�X�U�N�����R�j���A�ނ�̃A�C�f���e�B�e�B�i���ȓ��ꐫ�j�̊m�����߂����B�������A��쎁�́A����̐��N������̒����f�[�^���Ɋ�Â��A�ɉ����ĕω�����u�����I���ȁv�̊g��̎����������B���̏�ŁA������]���̒m���̂悤�ɖ�莋����̂ł͂Ȃ��A�����I���Ȃł����Ă��A��萶���₷����������Љ�̂��߂ɐ��������Ƃ����d�v�Ƃ����B
�@�u��Ƃ苳��v�ł�����u���v�ɂ��ẮA�w�͒ቺ�ᔻ�̗��ɏo��A���т̂悢�q�́u�\�͂�O��I�ɖ������Ɓv�A�悭�Ȃ��q�́u���ы�������~��邱�Ɓv�̓�d�̈Ӗ������悤�ɂȂ����Ɛ�쎁�͎w�E����B���̏�ŁA�u���Ȃ̑������́A��̌��ւ̉ߓx�̈ˑ��ɂ�郊�X�N��ጸ������v�ƁA�����̎�҂Ɏ�������L�ׂ悤�Ƃ���B
�@�]�҂��A���k�̌��݂̌��������Œ�I�ɂƂ炦��Ƃ�����A���t�ɂ����k�ɂ��悭�Ȃ��ƍl����B������܂�Ƃ܂Ƃ܂��Ă��܂��̂ł́A�]�܂��������Ƃ͌ĂׂȂ����낤�B��������̌��́u������v�́A���l�ȏɂ����āA���l�ȉӏ������点�������A���������Ă��������B
�@�܂��A���k�ɗF�B���o�Őڂ��Ă��炨���Ƃ��鋳�t������Ƃ�����A����͌����I�ł͂Ȃ��Ƃ�����B�ނ���A���l�ȗF�B�Ɛڂ���Ƃ��́u�����I���ȁv�Ƃ͈قȂ�u�x���҂ɑ����@�v���w�������B�ًc�\���������Ă悢���낤�B��������A�u�����I���ȁv���������u�����I���ȁv�̊m�����\�ɂȂ邩������Ȃ��B����ɂ����ẮA���̂悤�ɂ��āA���k�̎��ȓ��Θb��[�߁A�u�����Ƃ͉����v�̒Nj����x�����ׂ��ƍl����B

�s�����Љ�̒��̎�҂����|��w�������Q�T�N���猩��ߋ��E���݁E����
�@�u�s�����Љ�v�ɂ����āA���邢�������܂��������҂ł��Ȃ���҂������A�����̂��߂ɓw�͂����茻����y���݂����Ƃ����u���������͓̂��R���Ƃ������̎Љ�w�҂̌����ɑ��āA���́u����ł��A�ނ�͂��̕s�����ȓ�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ǝw�E����B���ƌ���s�����Љ���Ă������k�ɑ��āA�u�w�Z�ŗF�B�Ƃ��鍡���y�����v�����łȂ��A�\�������ɂ����Љ�̒��ł����Ă����Ȃ̈ʒu���߂����đ��Ƃ��Ă�����悤�x������K�v������
�@�Ћˎ��́A��҂��u�V�l�ށv�ƌĂ�Ă�������1987�N����A�u��Ƃ苳�琢��v��2012�N�܂ŁA�T�N�����ɑ�w���������s���Ă����B�{���ł́A�����Ɋ��S��w���n�w���U�T�Q�l�ɑ��Ď��{�����Q�O�P�Q�N�������ʂ͂��Ă���B
�@���ʖ����ɂ��ẮA����������Ȃ��v�̖����𖼏�����ق����悢�A�Ǝ��玙�͏����̂ق��������Ă���A�u�����ɕ��S����v���u�v���ł��邾�����́v�A�o�Y������d������߂�A�j�炵���E���炵���ƌ���ꂽ��������ȂǁA�ێ�I�X��������ꂽ�B�e�q�W�ɂ��ẮA�e�̂悤�ɂȂ肽���A�q�ǂ��̂܂܂ł������ȂǁA���R���Ȃ���҂Ƃ����X��������ꂽ�B�F�l�W�ł́A�Ƃ��ɏ��q�w���̏ꍇ�́A���������d������A�ڂɂ��₷����ʂň�l�ł��邱�Ƃ̃}�C�i�X�C���[�W���傫���Ȃǂɂ��āA�Ћˎ��́u�Ȃ��萢��v�̓����ƂƂ炦��B��Ƃ��Ă͐V���A�p�\�R��������A�X�}�z���}�������B�Љ�ӎ��Ƃ��ẮA�Ƃ��ɐ푈�̕s���ɂ��āA�j�푈���N����A�푈�Ɋ������܂��ȂǂƂ���w�����������B�d�Ԃ�o�X�ŐȂ�����A�n��s���ɎQ�����Ă���Ȃǂ����������A�Љ�^���ւ̎Q���ӗ~�͌������B���́A������u�₳��������v�̓����ƂƂ炦��B�����ӎ��ɂ��ẮA�����Љ�����A�����Љ�A�����Љ�𗝑z�̎Љ�Ƃ���w�����������B���q���̊C�O�h���A�V�c���j���D��p���Ɏ^���A���̊ۂւ̈����S���������B�������Ƃ��ẮA���������x�����サ�A�����ڕW�Ƃ��ẮA���̏\�N�Łu�L���Ȑ����v������A�u�Ȃ��₩�Ȗ����v�u���R�Ɋy�����v���������B�u�]�E�͂Ȃ�ׂ����ׂ��ł͂Ȃ��v���������B�o���ӗ~���������A���q�͂��̏\�N�Łu�C�y�Ȓn�ʂɂ������v�������A�j�q�͍���A�u�V��ŕ�炵�����v���}�������B���͂�����u�s�����Љ�̒��̂�Ƃ萢��̐������I���v�̓����ƂƂ炦��B
�@�u�s�����Љ�v�ɂ����āA���邢�������܂��������҂ł��Ȃ���҂������A�����̂��߂ɓw�͂����茻����y���݂����Ƃ����u���������͓̂��R���Ƃ������̎Љ�w�҂̌����ɑ��āA���́u����ł��A�ނ�͂��̕s�����ȓ�������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ǝw�E����B���ƌ���s�����Љ���Ă������k�ɑ��āA�u�w�Z�ŗF�B�Ƃ��鍡���y�����v�����łȂ��A�\�������ɂ����Љ�̒��ł����Ă����Ȃ̈ʒu���߂����đ��Ƃ��Ă�����悤�x������K�v������ƕ]�҂͍l����B

�@���q�͒j�q�|���q�͂�g�ɂ����j�q���V�����s���n��o��
�@�{���́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u��������J���l�����m�ۂ��邽�߂ɁA�Ƃɂ���������j���Ɠ����悤�ɓ�������v�Ƃ������Ƃ�����ڕW�Ƃ���E�ւȂ炦�̉��I�Ȕ��z�⍆�߂ł͂Ȃ��A�X�l�������̖{���̍K�������߁A����ɉ�������������l�X�ȃ`���C�X�̒�����I���ł��A��Ǝ�w����Ǝ�v���A�o���o���̃L�����A���q���j�q�����ėǂ����̒��B���A���{�Љ�ɍł��K�v�Ȃ��Ƃ́A���ׂĂ̓�����O�������������邱�ƂƂ����B
�@���c���́A�}�[�P�e�B���O�̎��_����A�u��҂̏����v�����^���Əq�ׂ�B�ŋ߂̎�N�j�����u���C���Ȃ��v�u�Ȃ�Ȃ悵�Ă���v�ƌ����錴���́u���q�́v��g�ɂ����}���ȕω��̌��ʂ��Ƃ����B���͂�u�j�炵���v�Ƃ������t�͒ʗp�����A�v���v���ɗ����A���e��_�C�G�b�g�ɊS���������s�ɂ��q���A����ȁu���q�͒j�q�v���䓪���Ă���Ƃ����̂��B�����āA���̓����́A�킪���̒����N��A�W�A�̍��X�ɂ��L�܂邾�낤�ƕ��͂���B
�@���́A�u���Ȗ����^���҂̖ڂ��ӎ��v�u���C�t�X�^�C���^���v��2���ɂ��4�ی��ŏ��q�͒j�q�ނ���B�Ƃ��Ɂu���C�t�X�^�C���~���Ȗ����v�ɂ��ẮA��ƂɂƂ��Ďs��g��̉\�����傫���Ƃ����B���̕��ނɃ��X�g�A�b�v����Ă���̂́A�ʂ�����ݎ��W�A�j�q��Ŏ��藿���A���q��ɗn������Ńg�[�N�A��e�ƒ��ǂ��A��������D���̒j�q�����ł���B
�@�㏑���ł́A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u��������J���l�����m�ۂ��邽�߂ɁA�Ƃɂ���������j���Ɠ����悤�ɓ�������v�Ƃ������Ƃ�����ڕW�Ƃ���E�ւȂ炦�̉��I�Ȕ��z�⍆�߂ł͂Ȃ��A�X�l�������̖{���̍K�������߁A����ɉ�������������l�X�ȃ`���C�X�̒�����I���ł��A��Ǝ�w����Ǝ�v���A�o���o���̃L�����A���q���j�q�����ėǂ����̒��B���A���{�Љ�ɍł��K�v�Ȃ��Ƃ́A���ׂĂ̓�����O�������������邱�ƂƂ����B
�@�w�Z����ɂ����Ă��A�}�[�P�e�B���O�̎��_�ɏK���A���̂悤�Ȏ�҂̎��Ԃ�ω��ɑΉ�����K�v�����邾�낤�B�����ɁA�]�҂́A�ނ�̎Љ���̏[���ɂȂ���悤�ɂ��邽�߂ɁA�]���̉��l�̓`���ƂƂ��ɁA���̎�҂̊e���C�t�X�^�C���ɋ��ʂ���V�������l���Ƃ��ɑn������K�v������ƍl����B

��Z�O�ɂȂ��Ă킩�������Ɓ|�l���͈�l�ł��ʔ���
�@����R�ƌ��d���邩��ǓƂł���A�R�~���j�P�[�V��������v�A�Ǘ��ł͂Ȃ��A�l�ƌ����Ȃ��̂ł��Ȃ��A�u������Ȃ��v�u��肩����Ȃ��v�V���O�����C�t�ɓO����Ƃ������t�́A�l���Љ�ɂ����ĎЉ�I�ɂ��[�����Đ����Ă������߂ɁA�����I�Ȏ�����^���Ă����B
�@�c���́A�ϋɓI�Ɍ���̍��������w�j�������Ă���B�l���̊y���݂͖��s���A�s�������Ƃ��낪��������s���B����́A�l���Љ�ɂ����āu���R�ɐ�����v�Ƃ����w�j�ł���A����̎Љ�d���̉��l�ςƈ�����悵�Ă���B
�@�c���́A���U��l�g�ŁA���p�ƒc�̂ɂ��������A�n��p�������ە\����`�҂Ƃ��Ċ��Ă���B�△�����̎��R�Ƃ����邾�낤�B�l�Ƃ��������́u�l���݂��Ɏx�������Ă���v�Ӗ����ƌ����邪�A�×��̍b�������ł́A��l�ŗ����A�����O�ɏo���āA�������n�߂悤�Ƃ�����A�l�Ɏ�������o���ď����悤�Ƃ����肵�Ă���̂ł͂Ȃ����Ɣޏ��͌����B
�@���Ƃ�ƁA�ߋ�������ڂɕω������܂�A����������ڂ͏��Ȃ��Ȃ�A�m��A�ے�̗��ʂ������A������߂ƌ�肪������B�ޏ��́A������A�����Ƃ��납�玩������Ղ��銴�o���ƌ����B���́u��萢��v�Ƃ������҂̊��o�ƒʂ�����̂����肻�������A��҂́u���v�Ɍ����Ă�����̂�ޏ�����w�ԕK�v�����낤�B

���܂ł���Ђ�����Ǝv���Ȃ�!
�@���҂Ƃ̑Η��⎄�����ւ̋]��������悤�Ƃ��鍡�̎�҂��A�������Љ�̒��łǂ���Ă邩�B�쓇���́A�Ј�����Ă�u�C�N�{�X�v���K�v���ƌ����B����́A�����̎������ɔz�����Ȃ���A�ƐіڕW��B��������Ƃ����u�V�����Ǘ��E���v�ł���B���̗v���́u�����̎������ƃL�����A���������Ă���v�u������d���Ǝ������𗼗������Ă���v�u�ƐіڕW�̒B���ɋ����R�~�b�g���Ă���v�̂R�ł���B���́A�d��(���[�N)�Ƌ��ɁA������(���C�t)�ƎЉ��(�\�[�V����)�Ƃ����u�R�{���̐����v���l���������L���Ȃ��̂ɂ��Ă����ƌ����B
�@���́A���ԓD�_�g�b�v�R�Ƃ��āA�����쐬�A���[���A��c��������B���Ƃ��Ή�c�ɂ��ẮA�S�[�����߁A�����̎��O�z�z�A�l���i��̂R�Ŏ��Ԃ͂W���̂P�ɂȂ�ƌ����B�������A���̐��Y���Ƃ́A�A�E�g�v�b�g���C���v�b�g�ł��邱�Ƃ���A����ł��鎞�Ԃ̍팸���ȏ�ɁA���q�ł��鐬�ʂ����k�����Ȃ��悤�x������B���̂����ŁA�c�Ƃ��Ă���Ј���萬�ʂ��o���悤���߂�B���́u���ʎu���v����҂Ɏx������Ă���悤���B
�@������\�߂�m�o�n�S�a�J���E�j�b�|���ɂ����ẮA�����_�ł͂Ȃ��A���ӂȂ��Ƃɒ��ڂ���B�����āA�Љ�Ŗ��ɗ��o����^���āu�v���S�v����ނ��Ƃɂ���āA�q�ǂ��̎��含�ƎЉ����Ă悤�Ƃ��Ă���B
�@�]�҂͍l����B��҂̋A���ӎ��̕s���Ȃǂ�ᔻ���邾���ł́A����͎n�܂�Ȃ��B�d�������łȂ��A�������A�Љ���̂��ꂼ��̏�ŁA�K���Ȑ��U�𑗂邽�߂̊�b�E��{���A�l���ɉ����Đg�ɂ������邱�Ƃ����A���U�w�K����̊w�Z����̖����Ƃ����悤�B

�q��ҁr�̗n��
�@�{���́A�K�������ɒ[�ɍ����Ƃ������Ƃɂ��āA�u�傫�Ȓn�k�ϓ��̂悤�Ȃ��́v��������Ƃ��Ă���B�K������������ƂɂȂ�C���t�����傫���ς���āA�����I�ɂ́A���Ȃ̗~�������낢��Ɩ������Ȃ���A����I�ȑΐl�W��z���Ȃ���A�T�ˁu�قǂ͂ǂ̖������ɐZ��Ȃ���v�����𐋂��Ă������Ƃ̏ł���Ƃ����B�������A�l�̃��x���Ŗڂɂ���̂́A�\�t�g�ȃC���^�[�t�F�[�X�̏��i�ł����Ă��A���̔w��ɂ��鋐��ȕ����̂́A�ɂ߂Č���ȋ����Ɖߍ��Ŏc���ȉȊw�Z�p�����̒��Ő�������Ă���B����N�����́A���̌����������ɓK������ŏ��̖{�i�I�ȑΉ��l����z�����Ƃ��Ă���Əq�ׂĂ���B
�@��莁�́A�u�F���D�n�����v�̏�g���Ƃ��Ă̐l�ނ́A�݂��ɂ������������Ȃ���A����������Ȃ��ɂȂ����Ƃ��A���ċߑ�̊�{�I���l�ςł���u���R�ƓƗ��v�����A�V�������L�̕��������o���Ƃ����ۑ�����B�����āA���̂��߂ɂ́A���w�����m�ۂ��A�S�̂Ƃ��Ă͊��e�ȑ��l����ۗL����Ƃ����u�d���^�A�C�f���e�B�e�B�v���d�v���Ƃ����B����́A�{���S�̂̃g�[���Ƃ��Ă̑����I���Ș_(�Ή��^�����炵��)�ƁA�ߋ��̈ꌳ�I�A�C�f���e�B�e�B�_�ւ̃A���`�e�[�[�Ƃ��Ă̕����ƂȂ���咣�ł���B
�@�܂��A��҂̍K�������ɒ[�ɍ����Ƃ������Ԃɂ��Ă͎��̂悤�ɏq�ׂ�B�K������������ƂɂȂ�C���t�����傫���ς���āA���Ȃ̗~�������낢��Ɩ������Ȃ���A����I�ȑΐl�W��z���A�T�ˁu�قǂقǂ̖������v�ɐZ���Ă����B�������A�w��ɂ́A�ɂ߂Č���ȋ����Ɖߍ��Ŏc���ȋ���������B����N�����́A���̌����������ɓK������ŏ��̖{�i�I�ȑΉ��l����z�����Ƃ��Ă���B
�@�]�҂͍l����B�����̓A�C�f���e�B�e�B�����ȓ��ꐫ�ƂƂ炦�A���̊m������҂̎����ɂƂ��Ă̕s�ς̉��l�Ƃ��ċ��犈����i�߂Ă����B�����A�u�d���^�A�C�f���e�B�e�B�v�ɂ���Č����K�����悤�Ƃ����҂ɂƂ��āA���̂悤�Ȏ��ȓ��ꐫ�������t���邱�Ƃ́A�l���Ă݂�Ύc���Șb���B���l�̓`���Ƒn����S�����炾���炱���A���Ԍ�F�̈��ՂȎ�Ҙ_�ɐU���邱�ƂȂ��A�Љ�w���̒m���������ꂽ��A�R�������肵�Ȃ���A��҂̎����x���̕�������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����邽�߂̏�Q�ɂȂ����
���Ȍ��肪�����A�ӔC�������ɖ߂��Ă��Ă��܂��l���Љ�B
��������Ƃ��̂��Ǝ��̂�]�܂����Ȃ��Ƃ���c�_������B
�������A�Ӓn�̂����҂́A���̂悤�ȍl�����͂��Ȃ����낤�B
��������A���Ȍ���⎩�ȑI���̗]�n���^�����Ȃ����ƂɈًc��\�����Ă����̂ł͂Ȃ����B
��҂̐l���̑I�������g�傷�邱�ƁA��҂̎��Ȍ���͂�{�����ƁA���ꂪ��҂������邽�߂́A�Љ�̐ӔC�ł���ƍl����B

�u�����v�ɏo���҂����|�d���E�Љ�W�E�n��Ԋi��
���������āu���Ȍ���v�œ����ɏo�Ă�����҂��A���͐��H�Â����Ă��āA����ɂ͖��j��āu�킪�ӂ邳�Ɓv�Ɂu�ǂ��A�����v�̂��A�t�^�[���A�h�^�[���̎c���Ȍ���B����ɂ����ẮA����ɑR���āA�n���̎�����ǂ���������̂��B
�@������́A�O�O��w�ٗp�����Z���^�[���s�������k�n���̎�҂̓������ւ̈ړ��Ɋւ��钲�����ʂȂǂ����ƂɁA���̂Ƃ���w�E����B�����ʂł́A���v��͍̂��w���҂ɕ��Ă���A�n��Ԉړ��̌o�ϓI�R�X�g���N���A�ł���u�b�܂ꂽ���v�ɐ��܂ꂽ�҂��u�b�܂ꂽ����v����ɓ���邱�Ƃ��ł���B
�@�l�ԊW�ɂ��ẮA�������ɂ́A�߂������N���̐e���A�����̗F�l������B�V���̗p���Ɍ��̏o�g�Ҙg��݂��Ă����Ƃ̗��ɓ���A�������Z�o�g�̐�y�����l������B���[�J���E�g���b�N(���H�t��)�ɂ��ړ��悪�W�����Ă��铌�����Ƌ{�錧�ȊO�ŏA�E�����Ƃ��A�ނ���Ǘ������ɒu�����Ǝw�E����B
�@�i�H�w���ɂ������āA�u�����̎���Ȃ̂�����A���k��l��l���e�n�̏A�E��A�i�w��Ɏ��ȑI���Ŕ�ї����Ă������Ƃ��]�܂����v�Ƃ͌����Ȃ��̂�������Ȃ��B
�@�Ȃ��A�������̑�w�ɐi�w�����҂ɂ��ẮA�o�g�n�Ō`�������l�ԊW�̌������A��l�b�g���[�N�̊g��ɂ��₤�Ƃ��������������[���B���̂ق��A�X���瓌�����ɏo��������҂ɑ���C���^�r���[���ʂ���A�J�����ꂪ�������A���Ԃ����X�Ǝ��߂ĐX�ɖ߂��Ă����Ȃ��Ŏc��҂̋�Y���������B�t�ɑ呲�Ŕ�r�I�����X�L�������X�o�g�҂��A�������Ő��ƂƂ��Ă����ߒ����������B
�@�����̒������s��ꂽ�̂́A�����{��k�Ђ̈ꃖ���O�ł������B�������A�u�����\�͂�v������E�Ƃ��A���x�ȋ���̋@����A��s�s�ɏW���v���Ă��錻��ɑ��āA�n��Ԋi���̐����Ƌ���@��ϓ��̂���������{���̈Ӌ`�́A�ނ��덂�܂��Ă���Ƃ����悤�B

�Љ�����тȂ����|����E�d���E�Ƒ��̘A�g��
���̒������Ƒ����q�ւ̋����V�K�J���͂Ƃ����T�C�N�������ꂽ���݁A���҂́A���̂Ƃ���V�����Љ�f�������B�u�g�D�̈���Ƃ��Ă̐g����^������v�����o�[�V�b�v�^����A�u���̏n�����含�Ɋ�Â��Đ��s�����A�ЂƂ܂Ƃ܂�̍s�ׁv�Ƃ��ẴW���u�^���Ј��ւ̈ڍs�B�����Ɍ������Đ����Ă������߂́u���ԓI�A�J�v�Ȃǂ��x������u�A�N�e�B�x�[�V�����v�B�����āA�w�Z�̖������A�u�ی�҂�n��ɊJ���ꂽ�w�Z�v�A�u�Ƒ��ւ̃P�A�̑����v�ƈʒu�Â���B�u�Љ���܂��܂��Ȃ��Ȃ����v���݁A�u���܂��܂���Ă����v�c��Ƃ͈قȂ�J���ς���Ă�K�v������B����́u�Љ�J���^�v�̎��_�����������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B
3320.html
�@���҂́A���̂Ƃ���Љ�̂ق���т��w�E����B�K�����@�\���Ă��Ȃ��Ƃ���ɂ���Ɂu�K���ɘa�v�Ɓu���R���v���������ށB�������i���͊����Ă���Ƃ���ɂ��������̒��߂���_�_���������ށB���݂ɖ�������悤�ȁu���v�v���A�v�����̂悤�ɂ��Ǝ��{�����B���܂������Ȃ������܂������߂ɁA�Љ�̓��O�ɂ킩��₷���u�����v��u�G�v��������o���Ē@���B���̂����Ղ�𐰂炻���Ƃ���悤�Ȃӂ�܂����A�u�����l�v�̒��ɂ��u�ア�l�v�̒��ɂ��L�����Ă���B
�@�����{�̓�̓]�@�Ƃ��ẮA�Ζ���@�ƃo�u������������A�Ƃ��Ɍ�҂ɂ��ẮA���S���Ǝ҂̑���ȂǁA�u�ꂪ��������ԁv�Ƃ��Ă���B����ȑO�́u�����{�^�z���f���v�ɂ����ẮA�d���E�Ƒ��E����Ƃ����O�̎Љ�̈悪���S�Ɍ�������Ă����Ƃ���B����ɂ����ẮA���I�x�o�̏��Ȃ��̒��ŁA���̒������Ƒ����q�ւ̋����V�K�J���͂Ƃ����������ŁA�Љ�����ʂ�u�܂���Ă����v�Ƃ����B�܂��A���̗v���Ƃ��ẮA��ܔN�܂ŋ���n�k���N���Ȃ������Ȃǂ́u�K�^�v�Ɍb�܂ꂽ���Ƃ�����ƌ����B
�@��ܔN�̓��o�A�w�V����̓��{�I�o�c�x�́A���Ј��̐V�K�̗p�̗}���ƁA���l�Ȍٗp�`�Ԃ̔Ј��̊��p�ɂ�鎖�Ƃ̈ێ��̎p���Ɂu���n�t���v��^�����B����ȍ~�A�u�Ƒ���H�킷�v�ɑ��邾���̎����������Ȃ��j���̔����i�Ƃ����B�܂��A�]�T�w�̒��ɁA�s�����Љ�ɑ��ĉߏ�ȂقNj���M�S�Ȑe�����ꂽ�B�l�Z�l�����ɁA�m��3�w�N����̂��Ƃ��w��ł���҂ƁA�Ƒ��̍�����s�a�ɋꂵ��Ŋw�K�Ɍ������Ȃ��҂�����A���̋���i���ƁA�ƒ납��̊��҂�v���̋��܂�̒��ŁA���t�͔敾���Ă���Ƃ����B
���҂́A���Ƃ�菭�Ȃ������Z�[�t�e�B�l�b�g����̂Ă��A��Z��O�N�����ɂ́A�q�ǂ�������ƒ�قǐ����ی�z���艺����ꂽ���Ƃ������A�u�z���̂��̂����Ă���̂ɁA���̎��͂��^���ԁv�Ɣᔻ����B
�@���҂́A�u�������܁v��R�~���j�P�[�V�����\�͂Ȃǂ̕s�����ȍ̗p���ᔻ���A�u�g�D�̈���Ƃ��Ă̐g����^������v�����o�[�V�b�v�^����A�u���̏n�����含�Ɋ�Â��Đ��s�����A�ЂƂ܂Ƃ܂�̍s�ׁv�Ƃ��ẴW���u�^���Ј��̎������咣����B
�@�Z�[�t�e�B�l�b�g�ɂ��ẮA�u�A�N�e�B�x�[�V�����v�Ƃ��������ꖇ�̕z�c��~���A�����Ɍ������Đ����Ă�����u���ԓI�A�J�v�Ȃǂ̎x���̗L�������咣����B
�@���҂́A�ȏ�̊ϓ_�ɗ������d���E�Ƒ��E����̑o�������f���ƕx�̍ĕ��z�ɂ��Ŏ��̑�����咣���A���̃��f���ɂ����āA�w�Z�̖������A�u�ی�҂�n��ɊJ���ꂽ�w�Z�v�A�u�Ƒ��ւ̃P�A�̑����v�ƈʒu�Â���B
�@�����āA�c�㓙�̑���ȍ��͂ƌ��͂�����w�̖��S�ƁA���ȐӔC�_�ɂ�鎩���ւ̔ے�I�ŗ⍓�Ȏ��_�Ȃǂ̏�Q�̂Ȃ��A�l�Z��O���ȉ��̑w�̓��{�^�z���f���̕ϊv�Ɍ������s���ɒ��ڂ���B
�@�u�Љ���܂��܂��Ȃ��Ȃ����v����ɂ����āA�ǂ������J���ς��������q�ǂ���������Ă�悢�̂��A�l�������K�v�����낤�B

���Z�����[�L���O�v�A�|�u�����Ȃ��n���v�̐^��
�u7�l��1�l�v�́u�n����ԁv�̍��Z���ɂƂ��āA��������҂����߂̃_�u�����[�N�͓�����O�ŁA�����Z��̐��b��Ǝ������Ȃ��A�u���d���v��w�����댯������B���̂قƂ�ǂ́u�Ƒ��̂��߁v�ɓ����Ă���A�����Č������ɐ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�����āA�ŐV�t�@�b�V�����i���͒ቿ�i�ȃt�@�X�g�t�@�b�V�����j�ɃX�}�[�g�t�H���i���̓��C�t���C���j���u���ʁv�Ɍ�������_�ł��A�����͒��ӂ𑣂��B�����́A�u�����Ȃ��n���v�ɂ��āA�����x���S�i�K�ɕ��ނ��A����ɂ͕n�������̐�i�n�ł���C�M���X�ŊJ�����ꂽ�u���D�w�W�v�i���@���������j��p���āA���������������g�݂��Љ��B���̌��ʁA�@���I�����������ɕK�v�ȁu���v�A�A�\�[�V�����L���s�^�����l�Ƃ̂Ȃ���A�B�q���[�}���L���s�^���������o���̂R�̌��@���w�E����B
�@���҂́A����������Ԓ��ł��V�t�g�������Ă��܂��u�u���b�N�o�C�g�v�ɑ��āA�u���������Ȃ��ƓX���܂��Ȃ��v�ƍl���A�f��Ȃ��ӔC���̂���܂��߂Ȑ��k�̗��������B�����A�w�K�ӗ~���킩�Ȃ��܂܁A��������݂̂ɒǂ���鐶�k�ɑ��ẮA�������ɂ������������邱�Ƃ����A���Ƃ��o�C�g�ɂ����Ă����ݎ�e�ł���W����������A�Љ�I�ȍL�����삩����̂�������A�l������ł���悤�ȗ͂���ނ��Ƃ����d�v�ł��낤�B

�u��x����v�̃W�����}�[�������p�͂Ȃ����s����̂�?
�@�G���[�g�̊��ɂ́A�D�P�����ɂ��Ă͖��v��ŁA�܂��A�����O�ɉƎ����S�ɂ��đ���Ƙb�����������Ă��Ȃ��B���ލ��Ƃ����āA�����Ɠ����ȏ�̎��Ԃ̂Ȃ������I�Ԃ��A�C�O�o���ɔ�щ��v�����邢�Ǝv���Ă��܂��B���������A�������A��肪���d���̂��߁A���A�ɕs�s���ȐE���I��ł��܂��Ă���B���ׂĂ����Ȍ���ɋA������A�Љ�ɑ��閳�֗^���L���邱�̂悤�ȏɑ��āA�M�҂́A�u�����̍\�����^���A�V�������l�ݏo���A�Љ��ς��Ă����l�ނ���Ă�v�悤����B�]�҂͎��̂悤�ɍl����B�G���[�g���q�Ƃ����ǂ��A��ʂ̌���N�Ƌ��ʂ̉ۑ�������Ă���B�����Љ�ɂ����ďd�v�Ȃ̂́A���Ȏ��������ȓ��Ŋ����������ɁA���҂Ǝ��Ȏ������݂��Ɏx�������Ƃ������Ƃł���B�v�Ƃ��R�~���j�P�[�V�������Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E���n��̖����̃��[�_�[����Ă邽�߂ɂ́A���̂悤�Ȏ��_�����߂���B
3390.html
�@���쎁�́A�P�X�X�X�N�̉����ϓ��@�ȍ~���Ђ̋����o�̈ꗬ��Ƒ����E���q�𒆐S�ɁA�P�T�l�̃G���[�g���q�̈�x�擾��̍��܂�ǂ��B�ޏ������́A�j���݂Ɏd���Ŏ��Ȏ������邱��(�o���L����)�ƁA���߂ɏo�Y���Ďq��Ă���Ƃ����u�Y�ߓ�����Ă�v���b�V���[�v�̃W�����}�Ɋׂ�Ƃ����B�u�������炢�v�Ȃǂƌ�����A���̏��q����u���̐l�����͏����g������v�Ƌ�����u�����B��x�����ɕ��E���Ă��A���肩��u�z������v�A�o���L�����̎��̂悤�ɂ͓������Ă��炦�Ȃ��B�ޏ������́A�q�ɂ͂��������Ȃ��B����͍����w�ƂƎЉ�I�n�ʂ�B�����Ȃ�����A���ƂȂ��Ă͊�ׂȂ��ł���̂��B
�@�G���[�g�̊��ɂ́A�D�P�����ɂ��Ă͖��v��ŁA�܂��A�����O�ɉƎ����S�ɂ��đ���Ƙb�����������Ă��Ȃ��B���ލ��Ƃ����āA�����Ɠ����ȏ�̎��Ԃ̂Ȃ������I�Ԃ��A�C�O�o���ɔ�щ��v�����邢�Ǝv���Ă��܂��B���������A�������A��肪���d���̂��߁A���A�ɕs�s���ȐE���I��ł��܂��Ă���B
�@���ׂĂ����Ȍ���ɋA������A�Љ�ɑ��閳�֗^���L���邱�̂悤�ȏɑ��āA���쎁�́A�u�����̍\�����^���A�V�������l�ݏo���A�Љ��ς��Ă����l�ނ���Ă�v�悤����B
�@�]�҂͎��̂悤�ɍl����B�G���[�g���q�Ƃ����ǂ��A��ʂ̌���N�Ƌ��ʂ̉ۑ�������Ă���B�����Љ�ɂ����ďd�v�Ȃ̂́A���Ȏ��������ȓ��Ŋ����������ɁA���҂Ǝ��Ȏ������݂��Ɏx�������Ƃ������Ƃł���B�v�Ƃ��R�~���j�P�[�V�������Ƃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�E���n��̖����̃��[�_�[����Ă邽�߂ɂ́A���̂悤�Ȏ��_�����߂���B

�u�A���v�Ɠ��{�Љ�\�������z����
�u���R�����v��u�����E�����v�̌��z�ɂ��A�w�����u�A�����v��V�����Ǝ҂ɒǂ����܂�Ă���B�����ɂ́A�����E�呲�Ȃǂ́u�^�e�̊w���v�ɉ����A�w�Z���Ȃǂ́u���R�̊w���v�ɂ��u�w���t�B���^�[�v�܂ő��݂���̂ɁB�t�ɁA�قƂ�ǂ̊w�����o�^����}�C�i�r�A���N�i�r�Ȃǂ̏A�E����Ђ́A���R����ʂ̉���ɂ��l�Ԃ̋�������������B�����͓w�͂��ĕ����\���̂��鋣���ł͂��邪�A�����Ċw������Ƃ��敾���Ă���B���������ɑ��āA�팩���́A�X�J�E�g�^�̋��l�T�C�g��A�J�E���Z�����O�ɂ���č̗p�\���̍�����Ƃ��w���ɏЉ��l�ރr�W�l�X��ƂɊ��҂���B���̕�������A�u�����������ł͂Ȃ����ƂɋC�Â��A��҂͎�҂Ȃ�̐����헪���l���悤�v�ƒ���B�����āA�u�U�����ꂽ���R�╽���͖\�͂ł���A���O����]�̓z��ɂ���v�ƒ��߂�����B�������A�]�҂́A�E�ƁA�ƒ�A�n��A�Љ���Ƃ�������̍L����Ȃ����āA���U�̏[���͂Ȃ��ƍl����B
�@�팩���́A��s������֘A�f�[�^�Ɋ�Â��A���̂悤�ɒ���B�u���R�����v��u�����E�����v�̌��z�ɂ��A�w�����u�A�����v��V�����Ǝ҂ɒǂ����܂�Ă���B�����ɂ́A�����E�呲�Ȃǂ́u�^�e�̊w���v�ɉ����A�w�Z���Ȃǂ́u���R�̊w���v�ɂ��u�w���t�B���^�[�v�܂ő��݂���̂ɁB����ɁA�����̑��Ɛ��͗ǂ��Ȃ��Ȃǂ́A�l�����������x�����O���s����B�����͓w�͂��Ă�����Ȃ������ł���B����ɑ��āA�قƂ�ǂ̊w�����o�^����}�C�i�r�A���N�i�r�Ȃǂ̏A�E����Ђ́A���R����ʂ̉���ɂ��l�Ԃ̋�������������B�����͓w�͂��ĕ����\���̂��鋣���ł͂��邪�A�����Ċw������Ƃ��敾���Ă���B
�@���̂悤�Ȏ��Ԃ̂Ȃ��A�팩���́A�X�J�E�g�^�̋��l�T�C�g��A�J�E���Z�����O�ɂ���č̗p�\���̍�����Ƃ��w���ɏЉ��l�ރr�W�l�X��ƂɊ��҂���B���̕�������A�u�����������ł͂Ȃ����ƂɋC�Â��A��҂͎�҂Ȃ�̐����헪���l���悤�v�ƒ���B�����āA�u�U�����ꂽ���R�╽���͖\�͂ł���A���O����]�̓z��ɂ���v�ƒ��߂�����B
�@�]�҂͍l����B��҂Ɋ�]��^���Ȃ�����ȂǑ��������Ȃ��B�������A�s�����̌����̂Ȃ��ŁA�����̎�҂��ꂵ��ł���B�����͗L����Ƃւ̏A�E��]�ɑ�\�����悤�ȁu��]�v�̎����̂��l�������K�v������̂ł͂Ȃ����B���w�Z�ł��N�ƉƋ��炪�n�܂����B�܂��A�E�ƁA�ƒ�A�n��A�Љ���Ƃ�������̍L����Ȃ����āA���U�̏[���͂Ȃ��B���̊�b�Â��肱���A�w���Љ�琶�U�w�K�Љ�ւ̓]�����ɂ�����w�Z����̖����ɑ��Ȃ�Ȃ��B

��N���ƎҔ���2014-2015�|�X�̑����Ɛi�H����ɂ����鑽�ʓI����
�@�u��ҁv�Ɓu�����v�̖��ɂ��ẮA����_�ŏ������ꂪ���ł���B��l�̎�҂��悢�`�ŎЉ�Ɂi�āj�Q�����A�����Ă����邱�Ƃ́A���܂��܂ȎЉ�ۑ���\���I�ɉ�������Z���^�[�s���ł���ƕM�҂�͍l���Ă���B�Ⴆ�A�������̎Љ���������Ă������Ȃ���҂ɖ��S�ł���A�ށE�ޏ���̌l�I�Ȗ�肾�ƌ��߂�������Ȃ�A���̖����͖��邢���̂ł͂Ȃ��B��l�̎�҂��������Ƃ��ł��Ȃ��܂܂ł��邱�ƂƁA�������Ƃ��ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ̃R�X�g�M���b�v��1��5000���~�Ǝ��Z����Ă���B����呲�ňꗬ��ƎЈ��̌o��������N���Ǝ҂������B�ߋ��̊w�Z���Љ�̊ϓ_�̂܂܂ł́A���U�ɂ킽��l�I�A�Љ�I�[���͎����ł��Ȃ��B
�@NPO�@�l��ďグ�l�b�g������T�[�r�X����3384���̑����f�[�^�����Ƃɂ�����N���Ǝ҂̎��Ԓ����̕��ł���B�O������2013�N�ɏ��߂Ĕ��s���ꂽ�B���e�[�}����������K�͒����́A�ق��ɂ͌�������Ȃ��B
�@��1�́u��N���Ǝ҂̌o���ɂ�镪�́v�ł́A�I�ʌ��2367���̃f�[�^��10�ォ��30��܂ł̔N��ŋ��A���ꂼ��̐E���A���Ɗ��ԕʂɕ����Ď��Ԃ͂��Ă���B10��ɂ��ẮA�������S�l�]��Ə��Ȃ��A�����I�ȗ��������Ȃ��B30��Łu���K�E�œ����Ă������A�d���ł܂����ސE������A���̏A�J�ɓ��ݏo���Ȃ��܂ܖ��Ɗ��Ԃ����������Ă����ҁv�ɂ��ẮA���w��w���������A���ޑw��1���߂�����B���K�E���̂��鑼�̑w���uPC���K�������v��������]���Ă���̂ɑ��āA�u�����ɍ����d�����������v�u�����鎩�M���������v����](6����)���Ă���B���i�ɂ��ẮA�u�ΐl�W�����v�i4�����j�����A�u�悭�^�ʖڂ��˂ƌ�����v�u�l�������Ă��܂��v�Ƃ����i6���O��j���ڗ��B�w�Z�ł́A�D�����Ƃ���ꂽ�������������̂��낤�ƕ]�҂͐��@����B
�@��2�́u�x���Ώێ҂ƃA�E�g�J���v�ł́A�O�ɏo�ėF�l�E�m�l�ȂǂƐڂ��Ă���l�͐i�H����ł��Ă���Ȃǂ̌X����������Ă���B��3�́u�W���u�g���ƒn���҃T�|�[�g�X�e�[�V�����̃A�E�g�v�b�g��r�v�ł́A��ďグ�l�b�g���_��ɉ^�p���Ă���L�����厖�Ɓu�W���u�g���v(���ꂼ��̔Y�݂��]�ɉ������ʓI�ȉۑ�ݒ�Ɋ�Â����A�O���[�v�s������{�Ƃ���p���I�ȃ��j���[)�ƁA�d�l�����i�ȍs���A�g���Ɓu�T�|�X�e�v�i�n���҃T�|�[�g�X�e�[�V�����j���i�H����ɋy�ڂ����ʂ��r���Ă���B���̌��ʁA����I�ȃf�[�^����ł͂��邪�A�L�Ӎ��ڂ̂��ׂĂɂ����āu�W���u�g���v�ɗ������邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�{���ł́u�T�|�X�e�̎x���ɐ���������Ă���d�l���̂�����v�ɋ^��𓊂������A�u�r�n�C���h�����l�փ|�W�e�B�u�ȉe����^����v�W���u�g���̈Ӌ`�Ɖۑ���N���Ă���B
�@���l�b�g�ւ̗����҂̂Ȃ��ɂ́A����呲�ňꗬ��ƎЈ��̌o��������N���Ǝ҂������ƕ����B�]�҂͍l����B�ߋ��̊w�Z���Љ�̊ϓ_�̂܂܂ł́A���k�̐��U�ɂ킽��l�I�A�Љ�I�[����ۏ��鋳��͎����ł��Ȃ��B�����̌l���A�������Љ�ɂ����āA���Ȕ������邽�߂́u������́v����Ă邱�Ƃ����A�����̊w�Z����̖����Ƃ����ׂ��ł��낤�B���̖{�ɂ́A�u�����炵��������v���āA�u�����炵����E�Ƃ�Љ�Ŕ�������v���߂̎x���ڕW�ݒ�̃q���g���������B��Ă���ƍl����B

�@�n����炵�̍K���Ǝ��
�@���҂́A�n����炵�Ǝ�҂́u�s�K�v�ɂȂ���Љ�I�r���̃��J�j�Y���ɏœ_�Ă�g�g�݁i�Љ�I�r�����f���j�ƁA�u�K���v�̉\���𑨂���g�g�݁i�Љ�I��ۃ��f���j�Ƃ̊W������B���̂����ŁA�u�K���v�̐������f���Ƃ��āu�o�ϓI�v���v�Ɓu���ݘ_�I�v���i��o�ϓI�v���j�v����ʂ���ϓ_�������B���Ƃ��A���ƂɈˑ�����������Ȃ��o�Ϗ���I�Ȓ��ԃR�~���j�e�B�ƁA����Љ�̐i����E�F�u�Љ�̐����ɂ��n���E�n��Ȃ���̋����Ƃ�����ʂ��w�E����B
�@���{�̎�҂���s�s��ڎw���Ȃ��Ȃ��Ă����ƌ����A��҂̒n���ւ̈ڏZ�E��Z�𑣂������I�ȓ������i�݁A�u�n����炵�̍K���v�ɂ��āA�ϋɓI�Ȕ��M���Ȃ���Ă���Ȃ��A�M�҂́A���̍K���̐��������ƎЉ�I�ۑ�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ���B�O��s�s���������n�����̓����̍��قƂ����ƁA�s���{���Ԃ̍��ق�A�����{�Ɠ����{�̍��ٓ�����肴������邱�Ƃ��������A�M�҂͂���������|�I�Ɂu�n���������_�s�s���v�Ɓu�����s���n�挗�v�̍��ق̎��Ӗ����d�v�ł���ƍl���A����������r���ɂ�������čl�@��[�߂�B
�@�����n�́A�L���s�s���̍x�O�n��i���|�S�{�����j�ƁA��������Ԃňꎞ�Ԕ��قǂ̒����R�n�̏��s�s�i�O���s�j�Ƃ�����̎����̂ŁA������u�n���������_�s�s���v�Ɓu�����s���n�挗�v�Ƃ����n��敪�̓T�^�Ƃ���B�ʓI�����ł́A��Z��l�A��ܔN�x�̎�Ғ����i��Z�`�O�Z��j�A���I�����ł͓������Z�\�l���x�̃C���^�r���[�����Ɋ�Â��āA�u�n�����牟���o���́v��A�n���w�����ł͂Ȃ��]���w�ɂ������͂Ƃ��Ắu�n��̂Ђ�����́v���ǂ̂悤�ɋ@�\���Ă��邩�Ȃǂɂ��Ď��ؓI�Ɍ�������B
�@�܂��A���C�t�X�^�C���̖��͂Ɋւ��鉿�l�ςŁA�u�c�Ɏu���̍K���v�Ɓu�n���s�s�u���̍K���v�̕��f�ɂ��Ď��̂悤�Ɏw�E����B�ꌾ�Łu�n����炵�v�̃��C�t�X�^�C���ƌ����Ă��A�X�т�_���̕��i�A���邢�͌Â������݂��L��������s���n�挗�̊��ƁA��^�V���b�s���O���[���ɏے�����鐶���̉��K��������Ƃ���n���s�s�����s�s���̊��Ƃł́A���̖��͂͑傫���قȂ�B�������A���̗��҂͋x���������ɂ����ďd�Ȃ荇���Ă���A�����s���n�挗�ɏZ��ł��邩��Ƃ����āu�c�Ɏu���v�ł���Ƃ͌���Ȃ��B
�@����ɂ��āA�M�҂́A�n����炵�Ǝ�҂́u�s�K�v�ɂȂ���Љ�I�r���̃��J�j�Y���ɏœ_�Ă�g�g�݁i�Љ�I�r�����f���j�ƁA�u�K���v�̉\���𑨂���g�g�݁i�Љ�I��ۃ��f���j�Ƃ̊W�����A���̂����Ŗ{���S�̂��т����͂̕��j�Ƃ��āA�u�K���v�̐������f���Ƃ��āu�o�ϓI�v���v�Ɓu���ݘ_�I�v���i��o�ϓI�v���j�v����ʂ���ϓ_�������B���Ƃ��A���ƂɈˑ�����������Ȃ��o�Ϗ���I�Ȓ��ԃR�~���j�e�B�ƁA����Љ�̐i����E�F�u�Љ�̐����ɂ��n���E�n��Ȃ���̋����Ƃ�����ʂ��w�E����B
�@�]�҂͍l����B�Љ�w�̂��̂悤�ȗ��̓I�c���́A����W�҂ɂƂ��Ď����ɕx�ނ��̂ł���B�����ɁA�Љ�w�͌���ϊv�ւ̊S�������B�Ƃ������A�������������ړI�Ƃ��Ă��Ȃ��B�������A����́A����܂ł̉��l�̓`���ƂƂ��ɁA�V�������l�̑n����ړI�Ƃ��銈���ł���B�Љ�w�̃��A���ȔF���ɏK���Ȃ�����A�����Ō����u�n���������_�s�s���v�Ɓu�����s���n�挗�v�̗����Łu�K���ɂȂ��鑶�ݘ_�I���l�v����҂ƂƂ��ɑn��o���K�v������Ƃ����悤�B

��\�ꐢ�I�̎�Ҙ_�|�B���ȕs������
1990�N��́u���X�W�F�l�v����̏ꍇ�A�^�悭���K�ٗp�̎d���ɏA�����Ƃ̂ł����҂��A�������o�ϊ��̂Ȃ��ʼnߑ�ȗʂ̋Ɩ��ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ�B�i�@�������v���w�@�d�_���ɂ���ĕٌ�m�̎��i���Ƃ�A���m�����Ƃ��Ă����v�𗧂Ă邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u�����w�����[�L���O�v�A�v���������݂�����Ă������B���̂悤�ɁA���������͎���̋]���҂��Ƃ������o������Ă����B����ɑ��āA2010�N��̎�҂����́A���q���̂Ȃ��ő�Ɉ�Ă��Ă����B�l�ߍ������ے肷��u��Ƃ苳��v�̐\���q�ł�����B����̑S�̂���`���Ȃ߂��u���X�W�F�l�v�Ƃ͈قȂ�A�b�܂ꂽ��҂Ƃ����ł͂Ȃ���҂̕��f�����̐���ł͌����ɂȂ��Ă��Ă���B�V���R��`���K���ɘa�����Ȍ��聨���ȐӔC�Ƃ����l���̗���ɂ��āA�Љ�w����̔ᔻ�͑����B�����āu�N�[���W���p���v�ȊO�͂����ȂׂĈÂ��B����ɑ��āA����́A���k�Ɏ��Ȍ���\�͂�g�ɂ������邱�Ƃɂ���Čl�ƎЉ�ɂƂ��Ă̖��邢�W�]�����o�����Ƃ���B����͂����ɂ���Ή\�Ȃ̂��B���J���́A�Îs�̃V�j�V�Y���i�T�ρE����j��ᔻ���A��ҕ����Ɋ�]�����o�����Ƃ���B
�@���̖{�́A����Z�N�ォ��ɓ�Z��Z�N��܂ł̎�҂ɂ��ď����ꂽ��\�I�ȏ����⌾�������グ�A����炪�����ꂽ�����̎�҂����̎p�ƁA���������������Y�o���������P��o���B
�@��P���ɂ����ẮA�o�ς̒�ƎЉ�s���̋�\�N��ɂ��āA��\�I��Ҙ_�҂ł���{��^�i��_����B�܂��A���S�K�N�������ɂ��ẮA���N�ƍ߂̋}���������͌��z�ɉ߂��Ȃ��Ƃ��A���ɂ䂭�҂̋ꂵ�݂ւ̑z���͂������A�u���E���Ȃ���v�Ƃ����K�͂��ȒP�ɓ��݉z����u�E�Љ�I���݁v�̏o���̏Ռ�������B
�@��Z�Z��N�̏���̐V���R��`�I���v�ɂ��ẮA�u���ȐӔC�v�Ƃ����L�[���[�h�ɂ��āA�u����ȏɒu���ꂽ�͎̂����̐ӔC�Ȃ̂�����A�l�𗊂炸�Ɏ��͂ł������������v�Ƃ����Ӗ��ł���Ƃ��A��҂͓���ł͂Ȃ����ƍU���̓I�ɂȂ����Ƃ��āA���̂悤�ɓ����́u��Ҙ_�v�ᔻ����B��҂������́A����ɖ҈Ђ��ӂ���Ă����B�����ȎЉ�w�҂͏A�E���Ă��Ƃ��o�Ȃ���ҁi�p���T�C�g�E�V���O���j�̋}�����A�s���ƔE�Ӎ����̌����ƂȂ��Ă���ƒf�����B�w�Z�ɂ��ʂ킸�A�E�����Ȃ��A���C�͂Ȏ�҂��w���u�j�[�g�v�Ƃ������Ƃ����s�����̂����̎���̂��Ƃł���B�u�Q�[���]�v�u�g�т��������T���v���̂��Ƃ������悤�ɁA�Q�[����g�ѓd�b�ɒ^�M�������ʁA���܂̎�҂͐l�ԂƂ��ė��Ă��܂����Ƃ����^���Ȋw�I�ȋc�_�����̎���ɂ͉��s���Ă����Ƃ����B
�@��Q���ɂ����ẮA�Љ���̌�������҂����̈ˑ��I�ȐS���ɋA���������A�̌������u�S����`�I��Ҙ_�v�ƌĂсA�����̘_�҂��Ȋw�I���@�Ƃ������͂ނ���u���C�t�R�[�X�K�́v�Ƃ��ĂԂׂ��u�펯�I�m���v�Ɉˋ����Ă����Ƃ���B
�@���J���́A���ȐӔC�_���x�z����Љ�ɂ����āA�Љ�I��҂͐����グ�邱�Ƃ�����ł������Ƃ��A��Z�Z�Z�N��̌㔼�ɂȂ�Ǝ�҂������g�����̃W�������ɎQ������悤�ɂȂ����Ƃ���B����܂ł̒��ق��������Ă����s����A�J�̎�҂������A�u����������I�v�Ƃ����u���v���グ�n�߂��Ƃ����̂��B
�@��R���ɂ����ẮA�N�[���W���p���ɂ��āA�u�|�s�����[�����̖L�`�v�Ƃ��A���Z�N�㖖�̗c���A���E�Q�����̋L���ƂƂ��Ɍ���A�����܂����I�[���ɕ�܂�Ă����I�^�N�������A��Z�Z�Z�N��̔��Έȍ~�ɂ́A���{�̃\�t�g�p���[�i���̍��̖��́j�̌���Ƃ݂Ȃ����悤�ɂȂ����Ƃ����B�����āA�|�s�����[�����́A����ȏɒu���ꂽ��҂����ɂƂ��Đ������]�Ƃ����Ȃ��Ă���Ƃ���B�܂��A�����������̐l�ԊW�́A�A�j����}���K��e���r�h���}����ؗp���Ă����u�L�����v�������邱�Ƃɂ���Đ��藧���Ă���Ƃ��A�|�s�����[�����́A��҂����̓��퐶���̂�������K�肷����ݐ���тт����̂ɂȂ��Ă��Ă���Ǝw�E����B����ƃW�F���_�[�ƍ��Ђ��������čL���葱����ł��낤�I�^�N�����̑��l��������Ɏ��߂������������]�܂��Ƃ����B
�@���J���͏q�ׂ�B����Z�N��́u���X�W�F�l�v����̏ꍇ�A�^�悭���K�ٗp�̎d���ɏA�����Ƃ̂ł����҂��A�������o�ϊ��̂Ȃ��ʼnߑ�ȗʂ̋Ɩ��ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ�B�i�@�������v���w�@�d�_���ɂ���ĕٌ�m�̎��i���Ƃ�A���m�����Ƃ��Ă����v�𗧂Ă邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u�����w�����[�L���O�v�A�v���������݂�����Ă������B���̂悤�ɁA���������͎���̋]���҂��Ƃ������o������Ă����B����ɑ��āA��Z��Z�N��̎�҂����́A���q���̂Ȃ��ő�Ɉ�Ă��Ă����B�l�ߍ������ے肷��u��Ƃ苳��v�̐\���q�ł�����B����̑S�̂���`���Ȃ߂��u���X�W�F�l�v�Ƃ͈قȂ�A�b�܂ꂽ��҂Ƃ����ł͂Ȃ���҂̕��f�����̐���ł͌����ɂȂ��Ă��Ă���B
�@�ŏI�͂ɂ����ď��J�q�́A��Z��Z�N�̎�Ҙ_�́u�X�^�[�v�ƂȂ����Îs�������ɍڂ��A�������͐V�����������͕ێ�I�ŌÏL���Ƃ�����ʐ����G���[�g�����N�j���Ɋ��}����A�ނ�����̒����̒n�ʂɉ����グ���ƕ��͂��Ă���B
�@�]�҂͍l����B���̂悤�ɁA�V���R��`���K���ɘa�����Ȍ��聨���ȐӔC�Ƃ����l���̗���ɂ��āA�Љ�w����̔ᔻ�͑����B�����āu�N�[���W���p���v�ȊO�͂����ȂׂĈÂ��B����ɑ��āA����́A���k�Ɏ��Ȍ���\�͂�g�ɂ������邱�Ƃɂ���Čl�ƎЉ�ɂƂ��Ă̖��邢�W�]�����o�����Ƃ���B����͂����ɂ���Ή\�Ȃ̂��B���J���́A�Îs�̃V�j�V�Y���i�T�ρE����j��ᔻ���A��ҕ����Ɋ�]�����o�����Ƃ���B���̊�]�ݏo���̂́A��҂Əo��Љ�̂��܂��܂ȋ���@�\�ɂق��Ȃ�Ȃ��ƕ]�҂͍l����B

�A��|��
�@�{���́u�v�w�W�͈�đ�������́v�Ə�������B���̒ʂ�Ȃ̂����A�]�҂́A����ȑO�ɑ傫�ȏ�Q������Ɗ�����B�v�w�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����ɂ��āA���鏗�q�w�����u�Ȃ����̂ق�����w�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�Ǝ��Ɍ������B�݂����u�����̂ق�����͂ǂ����邩�l����v�Ƃ����O�̂��̂����ꂩ���Ă���̂��B����̐��E�ł́A�L�����A�ɂ�����R�~���j�P�[�V�����͂̈琬����ɖڂ������Ă���悤�����A�l�̎������̊�@�ɂ��ڂ�z��K�v������B
�@�����⎟����̎������́A����ǂ��Ȃ�̂��B�����͋A��|�ǂ̒j�������̂悤�ɕ`�ʂ���B��ɍȂ̊�F�����������A�ȂƂ̂��Ƃ�ɔ��A�A������ɂȂ�A�d�����I����Ă���Ђɋ��c��A�܂������ƂɋA�炸�A�킪�Ƃ�ڂ̑O�ɂ��Ă��߂��̌����̃u�����R�ʼnƂ̓��肪������̂�҂B���ю��́A���ʂ̎�w����]�g���āA�u�v�̋C�����A�Ȃ̋C�������悭�킩��v�w���J�E���Z���[�v�Ƃ��Ċ������Ă���B
�@�����́A���ꂼ�ꎟ�̂P�O�^�C�v���w�E����B�u�A��|�ǂɂȂ�₷���v�v���C��ŗD�����^�A�䖝�^�A�������Ƌ��^�A�O�ʐl�Ԍ^�A�ʓ|���������^�A���q����܌^�A���e���C�������Ȃ����A��e���q�X�e���[�^�A��e���ߊ��^�A�������ꂵ�Ă��Ȃ��^�B�u�v���A��|�ǂ����₷���v�ȁ��������肵���ǂ��Ȍ^�A�����͂�����^�A���������^�A�����^�A�}�C���[�������ς��^�A�{�X�^�A�q�X�e���[�^�A��e������I�Ńq�X�e���[�^�A���e��D���^�A�j�����ꂵ�Ă��Ȃ��^�B�܂��A�̌��k�Ƃ��ẮA�Ȃ��|���v�́u��i�̂悤�ȍȁv�A�v����|���ƌ���ꂽ�Ȃ́u�f�B�x�[�g�v�w�v�Ȃǂ̎��Ⴊ�Љ��Ă���B�܂��A�u�A��|�ǂɂȂ郁�J�j�Y���v�Ƃ��ẮA�Ȃ́u�z���́v�Ɓu�ϑz�́v�A�u�������A�����邩�v�ƍl���Ă��܂��v�Ȃǂ���������B

����Љ�͂ǂ��Ɍ��������\�����̌����炵���J������
�@���҂́A�N�����̐��_�̕ω���ǐՂ��Ă������ʂ��A���̂悤�ɂ܂Ƃ߂�B�@�u�ߑ�Ƒ��v�̃V�X�e����̂ƁA�֘A���č�����`�I�Ȑ��̃������̉�́A�A�u�����������v�̑���ƕێ牻�A�B�q���p�I�Ȃ���́r�̍Đ��B�����́A�o�ϐ����ۑ�̊����A����ɂ�鍇�������͂̉����A���邢�͌����ɂ���āA��т������_�g�g�݂̂Ȃ��Ŗ����ɁA�����I�ɔc�����邱�Ƃ��ł���ƌ����B���҂́A20���I�̔ߎS�Ȑ��s�̍���ɇ@�ے��`�A�A�S�̎�`�A�B��i��`������B�����āA����ɑ��āu�V�������E��n�����鎞�̂����̎��H�I�Ȍ����v�Ƃ��āA�@�m��I�ł��邱�ƁA�A���l�ł��邱�ƁA�B���݂��y���ނƂ������Ƃ̂R��������B�����āA�u��̍זE���܂��[������ƁA���̈���̍זE���G������ď[������v�Ƃ��āA�Ō�Ɂu�������Ɉ�̉Ԃ��J�����A���łɐ��E�͐V�����v��搂��グ��B
�@�Љ�w�҂�80�ɂȂ��āu�Z���咘�v���������B���̖{�̕\���ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă���B�u�Ȃ���p�ɗ�����Љ�́A�����Đl�Ԃ̐��_�́A����ǂ̂悤�ȕ����Ɍ��������B�������͂��̌�̎���̌����炵���A�ǂ̂悤�ɐ�J�����Ƃ��ł��邩�B�O�������\�N�A���܁A�V���������������v�B
�@�]�҂͍l����B����͉��l�n���̊����ł���B�����҂��ו������ꂽ���؉\�Ȓm����������Ă���Ă��A���ꂾ���ł͑���Ȃ����Ƃ������B����̌���Ŏ��s���낵�āu�V�������E�v�Ƀ`�������W����K�v�ɔ�����B���̂悤�ȂƂ��A80�����w�҂̎v�������u�傫�Ȍ����v�̒�N�́A����Ɍg���҂ɂƂ��ėE�C�Â�����B

�e����n�܂�Ђ�������|�S���w��������Ղ��N����5�̃v���Z�X
�@���҂́A�ŏ��ɒ��肷�ׂ��͏A�J�E�A�w�x���ł͂Ȃ��u��������ɐe�q�W��������v���Ƃƌ����B���̂悤�Ȑe�q�̈������d������S���w�̒m���Ɋ�Â��A����5�̃v���Z�X�Ƃ��āA�Ђ�������킪�q�ւ̍l������ւ̑S�̑����������B�@��]����]��Ԃ���A�킪�q�̐S�Ɂu��]�̓��v���Ƃ���悤�ɐe�͈�ѐ��������Ďx���鎞���B�A�ӎv���l�K�e�B�u����{�Ƃ����A�z�������銴���e���������蒮�����B�B�ړI���S�̒��ɗN���オ���Ă���u����Ă݂����v�Ƃ����~���Ɋ�Â��A�������`�������W���͂��܂�B�C�L�\�������ۂɑ��҂�W�c�̒��ɐg�������A�Εׂɉ����Ɏ��g�ގ����̗L�\���Ɨ��̃o�����X�ɒ��ʂ��A�������鎞���B�D�A�C�f���e�B�e�B���u�����������ŗǂ��v�����āu�Љ�⑼�҂��������Ȏ����i���Ȃ��j�ŗǂ��Ǝv���Ă���ł��낤�Ƃ����m�M�v�����B���Ȃ킿�A�C�f���e�B�e�B�̊l���Ɏ��g��ł��������B�{���́A���̂ǐ����₷�����Ƌ�̓I�Ȏ��g�ݕ��A�Ђ�������̏�ԑ��A�ٌ������ɔ�������Ђ�������N�̌��t�̗����ɂ���Ӗ��Ɨ����̎d���Ȃǂ��A�e���ǂ�ŗ������Ď��g�߂�悤�ɏ�����Ă���B
�@�g8050(�n�`�}���S�[�}��)���"(���������蓖�l��50��A�e��80��)���[�������Ă���B���̂悤�ɁA�w��������50�܂łЂ������肪���������Ƃɂ��āA���c���́u���������̂͂Ԃ�Ԃ��B�₷�炬�̒��Ŏ��������̂͂Ԃ�Ԃ��Ȃ��v�Ƃ��āA���̂悤�ɏq�ׂ�B�u���ӎ��ŋN�����Ђ�������v���A�킪�q���g�̗͂����ʼn�������͍̂���A�u��]�v����u��]�v�₪�āu�����v�ւ̓��̂�Ŋт�����̂́u�e�̈��v�̂ق��ɂȂ��B
�@���c���́A�ŏ��ɒ��肷�ׂ��͏A�J�E�A�w�x���ł͂Ȃ��u��������ɐe�q�W��������v���Ƃƌ����B
�@�{���́A���̂ǐ����₷�����Ƌ�̓I�Ȏ��g�ݕ��A�Ђ�������̏�ԑ��A�ٌ������ɔ�������Ђ�������N�̌��t�̗����ɂ���Ӗ��Ɨ����̎d���Ȃǂ��A�e���ǂ�ŗ������Ď��g�߂�悤�ɏ�����Ă���B
�@�]�҂͍l����B�Љ�̈������Ă悤�Ƃ���w�Z����̗��ꂩ��́A�e�q�W�ɂ��{���I������]�߂Ȃ��P�[�X���������邾�낤�B�Ȃ��ɂ́A�����Љ�I���삩��A�Љ�Q���̈ӗ~���Ȃ��A���ԑ̂���l���āA�킪�q��ǂ��l�߂�e�����邾�낤�B�e�ւ̎Љ���k��e������ƌ����Љ�I�{��̎��_�����߂���B�������A���̍ہASOS���鐶�k�����ɑ��āA�u�₷�炬�̒��Ŏ��������̂͂Ԃ�Ԃ��Ȃ��v�Ƃ����l�P�A�̎��_��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
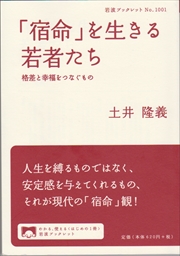
�@�u�h���v�����҂���: �i���ƍK�����Ȃ�����
�@�ߔN�A��҂�������芪���Љ���͈������Ă���B�i���̊g���n���A�[�������鎙���s�ҁc�A�Ƃ��낪����ŁA��N�w�ɂ�����K������������x�́A�t�ɍ��܂��Ă���B�Ȃ����B�l������̂ł͂Ȃ��A���芴��^���Ă������́A���ꂪ����́u�h���v�ςł���B���҂̌������A�Ⴉ�肵���ɐ����Љ��̌������x�e�����̋��t�ɂƂ��āA�����̎Љ�Ŕ|��ꂽ���Ґ����̍����́A���Ƃ��Љ���傫���ς���Ă��Ȃ��Ȃ��@�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂悤�Ȓ����N���L�̍������Ґ����������t���Ă͂����Ȃ��B��҂̍��̋��݂������w���������d�v���Ɩ{���͋����Ă����B
�@�Љ�������̈���ŁA��҂̍K������������x�͍��܂��Ă���B�M�҂́u�h���v���L�[���[�h�ɁA������Ƃ̔�r�A����ɂ��Љ�\�����̕ω����ӂ܂��Ă��̑������ۂ������������B���̎l�Z��ȏ�ɂƂ��āA�u�h���v�͎����̐l����A�s���R�Ȃ��̂ɂ���~���Ƒ������Ă��邪�A�O�Z��ȉ��̐l�����ɂƂ��āA�u�h���v�Ƃ͐l������̂ł͂Ȃ��A���芴��^���Ă������̂ł���A�܂��A�u�w�́v�Ƃ������t�́A�l�Z��ȏ�ɂƂ��āA�����̔\�͂⎑���̕s������₤���߂̉c�݂Ƒ������邪�A�O�Z��ȉ��ɂƂ��ẮA�w�͂ł��邩�ۂ����A�����̑f���̈ꕔ�Ƃ݂Ȃ����悤�ɂȂ��Ă���ƌ����B
�@�����̎Љ�̐��n���ɂ����ẮA���Ă̂悤�ɒ��z�I�ȖڕW�͋��ɕ����ɂ����Ȃ����B�����̎�҂������A�����̂悭������Ȃ��َ����̖ڕW�̂��߂ł͂Ȃ��A���̉c�݂̉ߒ����ꎩ�̂��y���݁A�Ȃɂ��ʂ̖ڕW���������邽�߂ł͂Ȃ��A�l�ԊW���̂��̂��y���ގ��ȏ[���I�Ȑl�ԊW��a���ł���ƒ��҂͕]������B�������A�u���D�������������Ȃ��悤�Ȕr���v���l�m�ꂸ�i�s���邱�Ƃɂ��ẮA�u�F���_�I��T�v���Ƃ��āA�O���ւƊJ���ꂽ�Ȃ���̂Ȃ��ŁA������L���A�i���ɋC�Â��A�����̐����グ��悤�i���Ă���B

�@�ǂ�Ȃ��Ƃ�������������l�|�t�����͂˕Ԃ��́u���W���G���X�v�̊l���@
�@���W���G���X�̂���e�́A�q�ǂ����s�o�Z�ɂȂ��Ă��A�u�䂪�Ƃ������Ă��������Ɍ�����`�ŕ\�����Ă��ꂽ�̂�����ǂ������v�ƂƂ炦��ƌ����B�����ɁA�q�ǂ��ɂƂ��Ắu������`�I���ԊW�v�̏d�v�����w�E����B����́A�e�́u���Ȏ�`�I�l�ԊW�v�Ƃ͈قȂ鑼�҂Ƃ́A���������W�A��܂������W�ł���B���ꂪ�A���W���G���X�̂���l�̃��C�t���C���ƂȂ�B�t���Ɉ�����`�I���ԊW�������Ă���l�͋����ƒ��҂͌����B
�@���҂̐l���_�́A1960�N�ォ��A�����̎�҂ɐ������̎w�j��^���Ă����B�{���́A�t���ł̉͂��Ӗ�����u���W���G���X�v�ɂ��āA�e�⋳�t�ł͂Ȃ��A����̗͂Ŋl��������̂Ǝ咣����B���҂���u���Ȃ��͑f���炵���v�ƌ����ď��߂āu���͑f���炵���v�Ǝv����l�A�����Ŏ����̑��݂��m�F�ł��Ȃ��ŁA���ȓ��ꐫ�𑼎҂Ɋm�F���Ă��炤�悤�Ȑl�A���҂���F�߂��Ď���̊m�F���ł���Ƃ����l�́A���ǂ́u�������g�������̓��e�ƂȂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�ƌ����B��̂̐������ɂ������ՂȎ�e�_�A���ȍm��_�́A�[���l�ԗ�����W������̂Ƃ����悤�B
�@���Ƃ��A���W���G���X�̂���e�́A�q�ǂ����s�o�Z�ɂȂ��Ă��A�u�䂪�Ƃ������Ă��������Ɍ�����`�ŕ\�����Ă��ꂽ�̂�����ǂ������v�ƂƂ炦��ƌ����B�����ɁA�q�ǂ��ɂƂ��Ắu������`�I���ԊW�v�̏d�v�����w�E����B����́A�e�́u���Ȏ�`�I�l�ԊW�v�Ƃ͈قȂ鑼�҂Ƃ́A���������W�A��܂������W�ł���B���ꂪ�A���W���G���X�̂���l�̃��C�t���C���ƂȂ�B�t���Ɉ�����`�I���ԊW�������Ă���l�͋����ƒ��҂͌����B
�@�]�҂́A��҂̋��ꏊ�̒��ŁA�����Ƃ��u��]�̕��v�ɂ������A����ł��Ȃ��^���ɐ������҂ɏo����Ă����B�ނ�́u�������g�������̓��e�ƂȂ�v���߂̒Nj��𑱂��Ă���B����������҂Ƃ̏o��́A��ʐN�ɂƂ��Ă��A�ʏ�̐l�ԊW�ȏ�̈Ӗ������B�w�Z����ɂ����Ă��A������`�I���ԊW�̂��鋏�ꏊ�ɂ����āA�����̐l�ԊW�Ƃ͈قȂ鑼�҂Ƃ̏o��̂Ȃ��Ŏ�̐�����߂�悤�A�q�ǂ��������x������K�v������ƍl����B
�T�u�J���`���[�ƃI�^�N�̉\��
�|�b�v�J���`���[���A�o�ϊE����M���܂Ȃ����Œ�������Ă���B
�������A��ҕ����̖{���I�����Ȃ��ɂ́A���҂Ǝ��Ԃ̃M���b�v���傫������B
�{���I�����Ƃ́A��҂̖ڐ��ɗ����������ƁA�l�Ԃ�Љ�ɂƂ��Ă̕����̈Ӌ`�Əd�v���Ɋւ��闝���̗��ʂ���̗����ł���B

���{�����̘_�_
�u�N�[���W���p���v�Ƃ��āA�|�b�v�J���`���[�̂`�b�f�i�A�j���A�R�~�b�N�A�Q�[���j�ɂ��o�ό��ʂ��A��l��������M�����ڂ𗁂тĂ���B�u�z�̓�����Ȃ���̐��E�v�����A�v�V�Ƒn�����ݏo���Ă����B
�F�쎁�́A�u���{�Ǝ��̔��W�v�𐋂��Ă���T�u�J���`���[���A�u��̐��E�v�Ɩ��t���A���̑��݂̑傫�����w�E����B�����āA�u��Ղ̕����𐋂��A����䂦�ɐ��x��J���N�����A���₩�ɉ����鍂��Ɠ��{�v���A�u���̐��E�̎p�ɂ����Ȃ��v�Əq�ׂ�B�u�z�̓�����Ȃ���̐��E�v�����A�v�V�Ƒn�����ݏo���Ă����Ƃ����̂��B
�@���ƓI�ɂ��u�N�[���W���p���v�Ƃ��āA�`�b�f�i�A�j���A�R�~�b�N�A�Q�[���j�̗A�o���d������鍡���A���k�ɂƂ��Ắu��̐��E�v�̑��݂��������F������K�v�����邱�Ƃ͊m�����낤�B
�@�㔼�ł́A�u���m�ߑ�̂��̂Ƃ͈قȂ��������ŋ쓮����V�������E�v�̏ے��Ƃ��āA�`�j�a48�����グ��B��������A�����A�I�����I���A�������Ƃ������V�X�e���̈Ӗ����ᖡ���A���{��`�ɂ���Đl�Ԃ̑z���͂���ꉻ����ǂ��납�A�~�]�����l�����A�ω������ƕ]������B
�@�������A���k�̑z���́A�n���͂́A�{���Ɉ���Ă����̂��B����́A�]���̕�����`�����邾���łȂ��A�V���ȕ�����n�o����c�݂ł�����B�T�u�J���`���[�́A�u�T�u�v�Ƃ������̂Ƃ���A���݂̎x�z�I�����ɑ��邽��Ȃ�u���ʂ̕����v�ɂƂǂ܂鋰�������B�]�܂��������n�o�̂��߂ɂ́A�A�т⋤���Ȃǂ̋���I���l��`����ƂƂ��ɁA�Љ�̌���ɖ��ӎ��������A����ɑR���镶���i�J�E���^�[�J���`���[�j�̒S������琬����K�v������̂ł͂Ȃ����B�����{��k�Ќ�A�l�X���J��n��̏d�v�����ɂ��āA��҂̔F���͍��܂��Ă���͂��ł���B�������A�������ŕ����͈炽�Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�I�^�N�I�z���͂̃��~�b�g�|�q���j�E��ԁE�𗬁r����₤
�I�^�N�́u�����ȕ�����f�[�^�x�[�X�����v�i���_�I�j�z���͂ƎЉ�I�L�p����F�߂A�Љ�`���҂̈琬�̂��߂̖ڕW�ɉ����āA�u�Ȋw�I�Ȍ����E�l�����v�⎩�ȂƂ̑Θb�̕��@�_�����������������ɂ͂���B
�@�I�^�N�������N�[���W���p���Ƃ��ċr���𗁂т�Ȃ��A���҂́A�����{�ʂȁu�I���G���^���Y���v���鐳�������������߁A�R�X�v���A�S���I�^�N�A�G���A�i���Q�[���A�����q�Ȃǂɂ��Ę_�q����B�܂��A���̕��������^���Ē����\������B�u�����ȕ�����f�[�^�x�[�X�����v�Ƃ��铌�_�I���́w����������|�X�g���_���x�A�u����̉F���̒��łȂ�������߂�v�Ƃ���k�c�ő厁�́w�o�����{�̃i�V���i���Y���x�A�u�����s�s��Ԃɉ�������v�Ƃ���X��È�Y���́w��s(�A�L�n�o��)�̒a���x�B��������A�I�^�N�����ɁA�ߑ����|�X�g���_���̉\���������������Ƃ�����̂ł���B
�@����ɂ����ẮA���̉\�����~�߂A����܂ł́u�傫�ȕ���v�Ƃ��Ă̗��j�w����ނ�ɓ`���邱�Ƃ����߂��悤�B
�@�I�^�N�́u�z���́v�ɂ��āA�Ґ́u�i�����g���j�Ȃ��S���I�^�N�Ȃ̂��v�Ƃ����₢�̂��ƂɁA�s��܂ł́u�D�Ԃ̎���v���u��z�̎���v�A���x�o�ϐ������́u�d�Ԃ̎���v���u���z�̎���v�A�ᐬ������́u�|�X�g�d�Ԃ̎���v���u���z�̎���v�A���݂́u�|�X�g�S���̎���v���u�ϑz�̎���v�ƕ��͂���B�����āA���̂悤�ȁu�z���͂̕����v��g�ݍ��V���ȎЉ���\�z����悤����B
�@�{��^�i���́A�I�^�N�E�R���e���c�����u�����̖��֘A���@�\�v�ɂ��A�u�I���G���^���Y���v�̋ȉ������z������͎̂��Ԃ̖��Ƃ���B����ɂ����ẮA�I�^�N�ւ̋����{�ʂȋȉ��͕��@������ŁA��l�̒~�ς��Ă��������E���l��`�����A����k�̓��I���E�́u�����v�Ɗ֘A�t�������A�ނ�̑z���̕ǂ���X�j�点��悤�ɂ������B
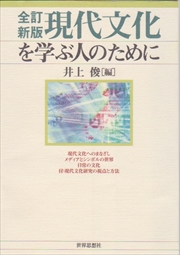
���㕶�����w�Ԑl�̂��߂ɑS���V��
�@���̖{�́A���ȂƑ��҂Ɛ��E�̕��ꂪ�A�V�j�J���ȁu���b�v���܂߂āA�Љ�I�������u�Ӗ��̒����v�Ƃ��Đ���������ƕ]�����A���̂悤�ɖ����N����B�u�����^�����v�Ƃ���������Ăɂ����Ȃ��������ł́A�����������u�ǂ����������̂��ƂŁv�ʗp����̂������ł���B�u�D�݂̕����ҏW�ł���v�Ƃ��Ă��A��������̂܂܌������ł���킯�ł͂Ȃ��B�{���ł́A���̎��_�̂��ƂɁA�e���҂��A���{���i�ɂ��|�b�v�J���`���[�A�l�����Ɓu�S���w���v�A�X�|�[�c�C�x���g�A�t�@�b�V�����A�ό��A�����Ȃǂɂ����錻�㕶���̌��͐��A���ȑa�O�A�s���R���A���ꂵ����������o���B
�@��㎁�́A���㕶����s�s�����A������A����Ƃ��ĂƂ炦��B�s�s�����Ƃ́A�����ɏے������悤�ȁu�������v�̕����ł���A�u�~�]���N���u�v�Ƃ��ď�������`�����Ă����B�S�ݓX�̂悤�Ȗ��͓I�ȁu��������ԁv�́u���������v�ł���ƂƂ��ɁA���s�ɒx�ꂽ���Ȃ��Ƃ��A�����������Ƃ��́u���������ւ̓����ƍ��فv������҂ɌĂыN�����B���̂��߂̏����������Ȃ��B���{���Ƃ����łȂ��A����ꎩ�g���A������銵��I�ȎЌ��p�^�[���ɗ��炸�A�ӎ��I�Ɂu���������v(�L����)�������āA���Ȃ��u��v���A���҂������Ȃ��悤�ɎЉ���𐬗������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����B
�@��㎁�́A�����Ő��܂�鎩�ȂƑ��҂Ɛ��E�̕��ꂪ�A�V�j�J���ȁu���b�v���܂߂āA�Љ�I�������u�Ӗ��̒����v�Ƃ��Đ���������ƕ]�����A���̂悤�ɖ����N����B�u�����^�����v�Ƃ���������Ăɂ����Ȃ��������ł́A�����������u�ǂ����������̂��ƂŁv�ʗp����̂������ł���B�u�D�݂̕����ҏW�ł���v�Ƃ��Ă��A��������̂܂܌������ł���킯�ł͂Ȃ��B
�@�{���ł́A���̎��_�̂��ƂɁA�e���҂��A���{���i�ɂ��|�b�v�J���`���[�A�l�����Ɓu�S���w���v�A�X�|�[�c�C�x���g�A�t�@�b�V�����A�ό��A�����Ȃǂɂ����錻�㕶���̌��͐��A���ȑa�O�A�s���R���A���ꂵ����������o���B
�@���̂悤�ȁu�D�݂̕��������ɕҏW�ł���v���̂悤�ɍ��o������l���Љ�ɂ����āA���ȂƎЉ�Ƃ��}�b�`���O�����A���Ȃ̐l���̕����K�ɕ҂ݏo����悤�x�����鋳��́A���₷���͂Ȃ����A�Ӌ`�[�����̂ƕ]�҂͍l����B

�f��͎Љ�w����
�ߔN�A�Љ�w�I�v�l��z���͂ɖR�������،����������Ă���Ɠ����͔ᔻ����B�Љ�w�̑傫�ȖڕW�͐l�Ԃ�Љ�́u���A���v�ɔ��邱�Ƃł���A�o�[�`�����Ȑ��E�̊g��Ƃ������܂��āA���̃��A���͎����Ɠ����ł͌��ׂȂ��Ȃ����Ƃ����B�]�҂������ł���B��X��|�M����u����������Ȃ鎖���v�ɑ��āA�X�g�[���[�Ƃ������̗ǂ����\�����u�l�ԓI�^���v�́A�����������炵�A�Nj������������Ƃ����C�����ɂ�����B���̂悤�ɂ��āA�ו������ꂽ�w��̈�̌��Ԃ߂��Ƃ��A�̌n�I�������[�܂�̂��낤�B
�@�����͎Љ�w�̎v�l�@�����̂R���ɕ����ē`����B�T�u�Љ�w�I�v�l�Ɋ����v�́A�T�^�I�����{�I�Ȃ��̂ŁA�����Ȃ��̂Ɏg���A�ÂтȂ������v�l�@�A�U�u�Љ�w�̎�����g����v�́A�Љ�w���瑽���z�����Ă��邪�A�Љ�w��L���ɂ��Ă����v�l�@�A�����ćV�́u����Љ��ǂ݉����Љ�w�v�ł���B����Ɋe�͂́A�@�f�悩��v�l�@�̂��ƂƂȂ�C���[�W�����ށA�A�Љ�w�I�v�l�����T�̈��p������Ȃ���������A�B����Ȃ�v�l�̔��W�⑼�̎v�l�@�Ƃ̘A�ւ�}��A�̂R����\������Ă���B
�@�͂��Ƃ�20�̎v�l�@���������A������������[���B�Ƃ��ɁA���@�̌�b�A�s�ׂƉ��Z�A���x�����O���_�A�W�F���_�[�^�Z�N�V���A���e�B�A�g�̋Z�@�A�g�D�ƏW�c�A�e�����A�_�u���o�C���h�A����Љ�_�A�K���P���Ǝ�̉��A�z���̋����́A���X�N�Љ�Ȃǂ̎Љ�w�I�Ȏv�l�@�́A��ÂȔ��f��������ɗ^����B�����w����i�H�w�����A����ɐ����鐶�k�ƍ����̎Љ�̌����ɓK���������̂ɂ��邽�߂ɁA�����͗L�v�Ȏ�����^����Ƃ����悤�B
�@�ߔN�A�Љ�w�I�v�l��z���͂ɖR�������،����������Ă���Ɠ����͔ᔻ����B�Љ�w�̑傫�ȖڕW�͐l�Ԃ�Љ�́u���A���v�ɔ��邱�Ƃł���A�o�[�`�����Ȑ��E�̊g��Ƃ������܂��āA���̃��A���͎����Ɠ����ł͌��ׂȂ��Ȃ����Ƃ����B�]�҂������ł���B��X��|�M����u����������Ȃ鎖���v�ɑ��āA�X�g�[���[�Ƃ������̗ǂ����\�����u�l�ԓI�^���v�́A�����������炵�A�Nj������������Ƃ����C�����ɂ�����B���̂悤�ɂ��āA�ו������ꂽ�w��̈�̌��Ԃ߂��Ƃ��A�̌n�I�������[�܂�̂��낤�B

�|�X�g�q�J���C�C�r�̕����Љ�w�|���q�����́u�V���Ȋy���݁v��T��
�@�u�ăt�F�X���q�v�́A�c�����ɔ��p�فE�����ٖK���N���V�b�N�������o�������҂������ƌ����B�����āA���̂悤�ȁu�������{�̍��������v���A�u�ăt�F�X�v�ł̎ʐ^�ʂ�̗ǂ��Ɓu���킢���v���l�b�g�Ŕ��M���Ă���Ƃ����B�ȏ�̊y���݂��A�{���́A�u�S��邱�Ƃ�S�����邱�Ƃɐs���Ȃ�����l�̕�炵�v�ƕ\�����Ă���B
�@�]�҂͍l����B�l�ɂ͌l�Ƃ��ĎЉ�l�Ƃ��Ă̐����Ƃ͕ʂɁA���̂��Ǝ��̂�������y���݂ɂȂ鎞�Ԃ�����B���ꂪ�Љ�ɂ�����V�������l�╶���̑n���ɂȂ���B�������A�����Ɍl�Ԃ̊i��������Ƃ���A�\�͖ڕW�����łȂ��A�n�����҂ɂ��������{�����悤�l�������B
�@���̖{�͌����B�u���킢���v�́A�ÓT�I�ȏ��炵���Ƃ����Ӗ�����A�`���I�ȋK�͂̈������甲���o���Ď����炵�����������Ɗ肤���q�����̊�]�̕\��ɕς�����B����̏��q�����́A��莩�R�Ɂu���킢���v���y����ł���B�����ł́A���܂��Ȃ����l���Ɛ������𑱂��鏗�q�������𖾂��邽�߁A�Q�[���A���b�N�A�����A�n���E�B���A���C�h�A���K�[���Ȃǂɂ�����u���킢���v��Nj�����B
�@�r�c���́A�u���킢���v���×�����Љ�ɑ���u�����I�ɖ����n�v�Ƃ����ᔻ�ɔ����A�����̊����̈�̊g��ȂǁA�Љ��葽�l�������߂鎞�ɕK�v�ƂȂ銴���́[�� �u���킢���v���ƌ����B�]���́u�j���I�v�Ƃ���Ă����̈�ɁA�����ƕʂ̃Z���X�≿�l�ς��������ށB���̂��Ƃɂ���āA�j�����������A������x�S�n�悭���̗̈�Ɋւ���悤�ɂȂ�Ƃ����̂ł���B�������́A�u�P�L�����v���܂߂��L�`�̃v�����Z�X�ɂ��āA�O�Z��A�l�Z��̏������Љ�v�������Ȃǂɂ��w�͌^�ł������̂ɑ��āA��Z��㔼�����Z��́A�u���܂�Ȃ���́v�����炵���̌��^���ƌ����B�����ł́A�u�j�����猩����v�Ƃ����ӎ�����������A�u���q�Ƃ��Ă̎����v�Ƃ�������������Ƃ����̂��B�i�c�ė����́A�ʓI�����̌��ʂ���A�u�ăt�F�X���q�v�́A�c�����ɔ��p�فE�����ٖK���N���V�b�N�������o�������҂������ƌ����B�����āA���̂悤�ȁu�������{�̍��������v���A�u�ăt�F�X�v�ł̎ʐ^�ʂ�̗ǂ��Ɓu���킢���v���l�b�g�Ŕ��M���Ă���Ƃ����B�ȏ�̊y���݂��A�g�����́A�u�S��邱�Ƃ�S�����邱�Ƃɐs���Ȃ�����l�̕�炵�v�ƕ\�����Ă���B

�d���Ȃ��������ɂ���ȁ|������Ӗ����Ăэl����
�@���҂́A�u�����I�ȋ�Y�v���甲���o�āu������Ӗ��v�����ނ��Ƃɐ��������N���C�A���g�̎p�𐔑����ڌ����Ă������ꂩ��A���߂Ȃ�����ɂ����āA�u�����I�Ȗ₢�v�ɂ͕K����o����������̂Ȃ̂ŁA�j�q���X�e�B�b�N�i�����I�j�Ȍ����ɘf�킳��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƒi����B�Љ�I�����␢�ԓI�펯�ȂǂɂƂ��ꂸ�A���ՓI�ɂ��̐��̐�����l�X�݂̍�悤�߂邱�Ƃ��ł������A�l�ɂ͕K����u�����I�Ȗ₢�v����������Ă���B���̖₢�ɋ�Y���邱�Ƃ́A���̐������ɂ͂Ȃ��u�l��Ȃ�ł́v�̍s�ׂł���A�����ɂ����A�l�Ԃ炵�����_�̓���������Ă���Ƃ����B
3680.html
�@�������Ƃ��������邱�ƁA���ł���������d����T���Ƃ����������������B�������A����ł͐l���͏[�����Ȃ����肩�A�����ԘJ���ŐS�g�Ƃ��ɐI�܂�Ă��܂��������B��J���́A�d�����S�̐l������E���A�V�������������������铹����ׂƂ��āA��ЁA�����A���̒��A���l�A�o���A�����u�̂��߂Ɂv������̂���߁A�S�̂����ނ��܂܂ɓ����V�Ԃ悤���߂�B�]�҂́A���E�ɏA���҂ɂƂ��ẮA�Y�܂����{���Ǝv���B�������A�Љ�I�s�K�����N�������q�ǂ������̂ق����A�u���ʂ̐l�ԁv���[�������������Ă���Ɗ����邱�Ƃ����邪�A���̃q���g���A���̖{���猩���邩������Ȃ��B
�@��J���́u������Ӗ���₤�v�Ƃ����u�����I�Ȗ₢�v���A�ł��l�ԓI�ȍs�ׂƂ���B�Љ�I�����␢�ԓI�펯�ȂǂɂƂ��ꂸ�A���ՓI�ɂ��̐��̐�����l�X�݂̍�悤�߂邱�Ƃ��ł������A�l�ɂ͕K���₱�̂悤�ȁu�����I�Ȗ₢�v����������Ă���Ƃ��A���̖₢�ɋ�Y���邱�Ƃ́A���̐������ɂ͂Ȃ��u�l��Ȃ�ł́v�̍s�ׂł���A�����ɂ����A�l�Ԃ炵�����_�̓���������Ă���ƌ����B
�@���́A�u������Ӗ��v��₤���ƂȂ�Ė��ʂȂ��Ƃ��Ƃ����V�j�J���Ȍ����ɂ���āA�u�����I�ȋ�Y�v������Ă���l�����́A�܂��܂����f�������Ă���ƌ����B���́A�u�����I�ȋ�Y�v���甲���o�āu������Ӗ��v�����ނ��Ƃɐ��������N���C�A���g�̎p�𐔑����ڌ����Ă������ꂩ��A���߂Ȃ�����ɂ����āA�u�����I�Ȗ₢�v�ɂ͕K����o����������̂Ȃ̂ŁA ���̂悤�ȃj�q���X�e�B�b�N�i�����I�j�Ȍ����ɘf�킳��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƒi����B
�@�Љ�I�����␢�ԓI�펯�ȂǂɂƂ��ꂸ�A���ՓI�ɂ��̐��̐�����l�X�݂̍�悤�߂邱�Ƃ��ł������A�l�ɂ͕K����u�����I�Ȗ₢�v����������Ă���B���̖₢�ɋ�Y���邱�Ƃ́A���̐������ɂ͂Ȃ��u�l��Ȃ�ł́v�̍s�ׂł���A�����ɂ����A�l�Ԃ炵�����_�̓���������Ă���Ƃ����̂��B
�@�܂��A�N���̊�@�́A�l���Љ�I�����ƂȂ��Ă������Ƃ���o���_�ł̗l�X�ȋ�Y�A�܂�A�E�ƑI����ƒ�����Ƃ��Ƃ��邱�ƂȂǁu�Љ�I���Ȏ����v�̔Y�݂��w�����̂����A���N���̊�@�̕��́A������x�Љ�I���݂Ƃ��Ă̖������ʂ����A�l���̌㔼�Ɉڂ�䂭�n�_�ŗN���オ���Ă���Â��Ő[���₢�A���Ȃ킿�A�u���͉ʂ����Ď��炵�������Ă������낤���H�v�Ƃ������A�Љ�I���݂�����̐l�ԑ��݂Ƃ��Ắu�����I�Ȗ₢�v�Ɍ���������Y�̂��Ƃ��ƌ����B�N���ɂ͏d�v�Ɏv�����u�Љ�I�v�Ƃ��u���ȁv�Ƃ��������̂��A�K�������^�̍K���ɂ͂Ȃ���Ȃ��u�����v�̈��ɉ߂��Ȃ��������Ƃ�m��A��l�̐l�ԂƂ��āu������Ӗ��v��₢�n�߂�Ƃ��A�܂��A����N���ɂ����Ă��A���̂悤�ȁu�����I�₢�v��������ƌ����B
�@���́A�C�\�b�v����̃A���ƃL���M���X�̗�������B�킪���ł́A�T�u�J���`���[�ɂ����Ă͐��E�����[�h���鐨���������Ă��邪�A�J���`���[���̂��̂ɂ��Ă͏\���ł͂Ȃ��Ƃ��A�L���M���X�̂悤�ɁA�����ɑς��镶���ݏo�����Ƃ��A����̋����ɉ����ׂ���Ȃ����߂ɋ��߂��Ă���ƌ����B
�@�]�҂͍l����B��J���̌����悤�ȕ��������߂�q�ǂ������́A���Ȃ����낤�B�����̎q�ǂ������̓T�u�J���ɑ���A���t������ɑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����͉������ł͈炽�Ȃ����炾�B�������A�ɉ������w�����l����Ȃ�A�����ɂ����������Ȃ�����u�����I�₢�v�╶����ǂ����߂�^�C�v�̎q�ǂ������ɑ��Ă��A�C�\�b�v����̃A���̂悤�ȁu�����v�����łȂ��A�L���M���X�̂悤�ȁu���v�̏[���̂��߂̎x������������K�v������B
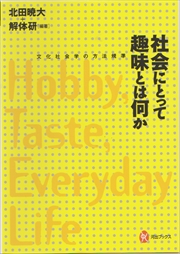
�Љ�ɂƂ��Ď�Ƃ͂Ȃɂ��|�����Љ�w�̕��@�K��
�@�I�^�N�A�T�u�J���Ȃǂ̎���A���҂Ƃ̍��ʉ������łȂ��A�t�ɕR�тƂ��Ă��@�\���Ă��邱�Ƃ͎����ł��낤�B���ہA�N���u�ʂ��̗F�l���n���o�g�̎�҂̓����蒅���������Ȃǂ̌��ʂ����̒����Ŗ��炩�ɂ���Ă���B�����A�K���I�ȍ��ʉ��Ƃ͈قȂ�Ǝ��Ȏ��Ȃ̊m���Ƃ����u�l���v�ƁA����ɉ����Ắu�َ��ȑ��҂Ƃ̌𗬂Ƌ��L�v�Ƃ����u�Љ�v�����A���炪�Nj����ׂ����l�Ƃ����悤�B���̂Ƃ��A�I�^�N�A�T�u�J�����܂߂����k�����̎�ɒ��ڂ��A�����邱�ƂȂ��A�@����Ƃ炦�Ė]�܂����l���ƎЉ�̌_�@�ɂȂ�悤���������邱�Ƃ��A���t�ɂƂ��ďd�v�Ƃ����悤�B
3640.html
�@���̖{�́A�u���f���[�̕������{�i�w���╶���I�f�{�j�̊T�O�ɂ�炸�A��������炷�e�C�X�g�i�Z���X�̗ǂ��A�����j�ɂ���č��ʉ�����A�K�����Đ��Y�����Ƃ����ނ̌����ɂ��āA�ʓI�����������Ĕᔻ�I�ɍČ�������B���Ƃ��A�������e�[�}�Ƃ���u��������̎�ҕ����v�Ƃ��ẴI�^�N�A�T�u�J�����ɂ����ẮA�ߋ��́u�e�C�X�g�_�v�͐��藧���Ȃ��Ƃ����B
�@���̂��߂̊�{�I�ȗ��_�I�E���@�I��������邽�߁A���̓_�ɂ��Ę_���Ă����B�u���w�͎��v�ƕ��w�҂����ɂ���ČJ��Ԃ���錾���̒����̂Ȃ��ŁA�����ɝ�������悤�Ƃ��u���w�v�̓e�C�X�g���ؖ�����ۏ؏��Ƃ��Đ����Ă��܂��Ă��邱�ƁB�u���҂Ƃ̍��ى��E���ʉ��E��z���v�Ƃ������_�_���A���j�N���Ȃǂ̃t�@�X�g�t�@�b�V�����ɂ����Ė��������ꂽ�̂��ȂǁA���[�h�A��z���̓T�^�I�Ȏ�i�Ƃ��Č��y���ꑱ���Ă����t�@�b�V�����ɂ����A��z�����_�̎Љ�_�Ƃ��Ă̐��\��������߂錮�����邱�ƁB�Ƃ��ɑ��҂Ƃ̍��ʉ�������߂Ă���ƌ����A�܂��Ƃ��ɑ��҂Ƃ̍��ى��ɊS���Ȃ��Ƃ����u�������v�Ƃ������Ȏ��s�I�E���Ҏ��s�I�ȃJ�e�S���[�̐������ɒ��ӂ��������ꍇ�A�u�������v�͍��ى��E��z����ڎw���m��~�ρE���l����ߑ�̋ɖk�Ƃ������邵�A����ňَ��ȑ��҂Ƃ̍��ى��ɊS�������Ȃ�������������߂����݂Ƃ��āA�����Ԃ�ƕ֗��Ƀ��f�B�A���]�ɂ����Ďg��ꑱ���Ă����J�e�S���[�ł���Ƃ������ƁB�ŏI�͂Ŗk�c�́A���ى��̘_�����̂��̂�����������Ƃ����_�ŋ��ʂ������A�u�n��v�ɃR�~�b�g����j���I�^�N�Ə����I�^�N�i�����q�j���A��i�̓ǂݕ��i��e�p���j�Ƃ����ϓ_���番�ނ��������ŁA�����������u�I�^�N�E�v�Ɉʒu����Ƃ��Ă��A�W�F���_�[�K�͋�ԂƂ����ϓ_���猩���ꍇ�A�����ɓ����ٖ��̏�Ԃɂ��邩�A�����F�Ƃ͕ʂ̊p�x����i����I�ɒ�`���ꂽ�ތ^�ɂ��ƂÂ��j��艻���Ă���B���ى��E��z���̘_�������������Ƃ�������E�ɂ�����j�����͉����Ӗ�����̂��B�����ɂ����Ă��A�W�F���_�[�Ƃ����ϐ��̏d�v�����m�F�����B
�@�k�c���́A�����q�iBL-�j���������̖���⏬�����D�ޏ����j���t�F�~�j�Y���̕\��ƂƂ炦�A�u����߂Đ������ꂽ�`�ŁA���ꂼ��̕��@�Œj�����S��`�I�Ȑ��E�ςɈًc��\�����ĂĂ���v�Ƃ���B�����āA�u�A�j����BL���ǂ��ł������v�Ƃ����l���ɑ��āA�����I�A�сE�Љ�I�ȊW���\�z�̎����̑��݂���ڂ�w���邱�ƂɂȂ�Ƃ����댯�����w�E����B
�Љ�v���E�Љ�ϊv��������҂���
��҂ɑ��āA�n��́u�����S�v���A�Љ�́u�Љ�Q���v�����߂Ă����B�������A���ꂪ����I�Ȃ��̂ł���ƁA�Љ�v���E�Љ�ϊv���Ă����҂Ƃ͒f���ł��܂��B��җ����̏�ŁA�n���Љ�Ɉ͂����ނ̂ł͂Ȃ��u�Љ�J���^�v�̎Q���@��̒��K�v�ł���B

�Љ��ς������l�̂��߂̃\�[�V�����r�W�l�X����
�@�l�b�g�Љ�ɂ����ď����A���k�����v���i���g�債�Ă��邱�Ƃɖ��ڒ��ł����Ă͂����Ȃ��Ƃ����悤�B���̏�ŁA�{��������u�V�����Љ�v���v�ɂ��āA�]�҂͎��̂悤�ɍl����B���̂悤�Ȏ�̓͂��͈͂ŎЉ�v���������Ƃ�����҂̎u���Ɏ~�߂����B��������ŁA�E�ƑS�ʂ��Љ�v���ɂȂ���Ƃ������ԂƔF�����L���Ă����������̂��B
�@�{���ł́u�t���^�C����NPO�����ƂƂ��Čo�c����v���߂̋�̓I���@��������Ă���B��莁�́A�u�Љ�N�ƉƁv�Ƃ���������������錾�t�����Ƃ��炭�����Ă��Ă��ꂽ�ƌ����A������ЁA�Вc�@�l�A���c�@�l�Ȃǂ̋敪�ɂ͂�������Ă��Ȃ��B
�@�ނ�2004�N��NPO�t���[�����X��ݗ����A���{���́u���ό^�E�K��^�a���ۈ�v�T�[�r�X���J�n�����B10�N��ɑҋ@�����������̂��߁u�������ۈ牀�v��n�݂��A���ꂪ��Ɂu���K�͔F�ۈ珊�v�Ƃ��č���ɍ̗p���ꂽ�B�{���ł́A�u���Ɏ��Ƃ��p�N���Ă��炢�A�Љ�ϊv���s�����@�v�Ƃ��āA���@������A�����Ɂu�́v�Ɣ�p�Ό��ʂ�`���A���ɂȂ���悤��������B�܂��A�u�����͂����ƌ�������v�Ɣᔻ����u�h���[���L���[�v�ɑ��ẮA�u�M�d�Ȉӌ����肪�Ƃ��B�ł��܂��A���͂�邯�ǂˁv�Ƃ����u�X���[�́v�̕K�v������ƂƂ��ɁA�ꊄ���炢�́u�悢�ᔻ�v������̂ŁA�u�Ȃ�ŁH�v�ƕ����Ԃ��A�ނ�̃��C�t�X�^�C���𐄎@���A�^�[�Q�b�g�Ƃ��ׂ��l����������Ƃ����A����u������́v�̋�̓I�������@�������Ă���B
�@�܂��A���̂悤�ȋ�̓I���@���l�b�g��ł����J���Ă���B���Ƃ��A�u�{�i�I�ȏ��������悤�i���ҁj�v�ɂ��Ă͎��̂Ƃ���ł���B�����o�[�̃��[���͂f���[���A�`�[���̗\��\�̓O�[�O���J�����_�[�A�t�@�C���̋��L�̓O�[�O����h���b�v�{�b�N�X�A�T�C�{�E�Y�A�n���O�A�E�g�A�ڋq�Ǘ��V�X�e���̓N���E�h�^�̃Z�[���X�t�H�[�X�𗘗p���āA�O���[�v�E�F�A�͖����ō\�z����B�܂��A�ΊO�I�ȏ�M�́A�܂��̓u���O�ƃt�F�C�X�u�b�N�A�c�C�b�^�[�̂R���g���B���܂��܂Ȋ����M���邱�ƂŁA�`�[�����A����ɂ̓X�e�[�N�z���_�[�i�x�����Ă����l����c�E��ƂȂǁj�ւ̊����ɂȂ�B�܂��A�������Ă����l�𑝂₷���ʂ�����B���܂��ܓǂ�ł��ꂽ�l���A�u�撣���Ă���l������B������`�������ȁv�Ǝv���Ă���邫�������Â���ɂȂ邩�炾�B
�@����ɁA���̂悤�ɓ��X�̊������~�ς���邱�ƂŐV������������Ă��ꂽ�l�ɂ́A���̒c�̗̂��j��A�����o�[�����̐l�ƂȂ��m���Ă��炦��c�[���ƂȂ�B���̂ق��A�u���O��t�F�C�X�u�b�N�A�c�C�b�^�[�̍X�V�����[�e�B���ɂ��邱�ƂŁA�����A�E�F�u�T�C�g�����������ɁA�X���[�Y�Ɉڍs���₷���Ƃ��������b�g������B�o�c�Ҍl����M���邱�ƂŁA�������g��m���Ă��炤�����@��ɂȂ�B�c�̂��̂��̂̏�M�͊w���C���^�[����Љ�l�v���{�m(���I�Z�\���������{�����e�B�A)�ɂ܂�����B�u���O�Ȃǂ̍X�V�͉��u�ł��ł���̂ŁA�ނ�ɂ܂����₷���d�����Ƃ�����B
�@�����āA�T�[�r�X�C���̑O�ɂ̓E�F�u�T�C�g���X�^�[�g������B���ꂪ�Ȃ��ƁA���p�҂ɁA�ǂ�������Ȃ��c�̂Ƃ̈�ۂ�^�����˂Ȃ��B�������Ȃǂł���������������A30���`50���~���炢�ł������̂ɂ���B���邢�͎Љ�l�v���{�m�ɂ��肢���āA�^�_���R�ł����Ă��炦��̂Ȃ�A����ɉz�������Ƃ͂Ȃ��B�m�o�n��\�[�V�����r�W�l�X�ɂ����炸�A�N�Ƃ̓S���́A�ŏ��͏������A�ǂ�ǂ�傫����ĂĂ����B�����ɂ����������Ȃ��ŁA�������̂������Ă����邩���l����̂��d�v���B�Ȃ��A�E�F�u�T�C�g�������Ă��A�t�F�C�X�u�b�N�ƃc�C�b�^�[�͐������Ă������B����A�u���O�̓E�F�u�T�C�g�Ɉڍs������̂��������낤�ƌ����B�l�b�g�Љ�ɂ����ď����A���k�����v���i���g�債�Ă��邱�Ƃɖ��ڒ��ł����Ă͂����Ȃ��Ƃ����悤�B

�C�m�x�[�V�������N�����g�D�|�v�V�I�T�[�r�X�����̖{��
�@�{���́A�C�m�x�[�V�������N�������߂ɂ́A�u�m���̑n���Ǝ��H�v���K�v�ł���A���̂��߂ɁA���̊W�i���ꃊ�[�_�[�̑P���ړI��v�����N�_�Ƃ������n�̏�Â���j�Əc�̊W�i�ړI��v������������W���I�Ȏ��H�́j�̑g�ݍ��킹���A�g�D�����蓮�����Ă����L�[�R���Z�v�g�ɂȂ�ƌ����B�]���̌o�c�w�ł����Ă����悤�ȁA�s���ƊE�ł̃|�W�V�������ɂ�鍷�ʉ���A�g�D�����̍ő劈�p�Ɋ�Â��������Ƃ����悤�ȃA�v���[�`�ł́A�C�m�x�[�V�����͋N�����Ȃ��Ƃ��A�Η��⊋�����u���ꂩ���ꂩ�v�̓Η��ł͂Ȃ��A�ɉ����āu�����������v�̓��Ԃ̃`�����X�ƂƂ炦�ď��z����悤����B�]�҂͍l����B��������[�_�[�V�b�v�Ƃ��āA�قȂ鉿�l�ς��������o�[����������u�c�̊W�v���Ȃ킿�g�D�E�W�c�ŖړI�����L���A���������邽�߂̈ӗ~��\�͂͂ǂ��{���悢�̂��B�u�Ǘ��E�ɂȂ肽���Ȃ��v�Ƃ�����҂�s�N�������Ă���Ȃ��ŁA�g�D�I�C�m�x�[�V�����̂��߂̋��������Ȍ��肷��u�l�v�̈琬���A����́u�Љ�`���ҁv�琬�̏d�v�ۑ�ƍl�������B
�@���҂́A�u�m�n���[�_�[�V�b�v�v�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B���H�m�Ƃ́A���ʑP�icommon good�j�⓿�ivirtue�j�̉��l��������āA�ʂ̂��̓s�x�̕����̂����Ȃ��ŁA�őP�̔��f���ł�����H�I�Ȓm���̂��Ƃł���B����̓I�ɂ����A�ʋ�̂̕����ł��傤�ǂ����ijust right�j���������邱�ƁA�����Ȃ���l���������ƁA�����ɑ��������f�icontextual judgement�j�ƓK���▭�ȃo�����X�itimely�@balancing�j���ł��邱�ƁA�Ȃǂł���B���̂��߂ɂ́A����6�̔\�͂��K�v���ƌ����B�@�P���ړI������\�́F���ʑP�⓿�̉��l��Ɋ�Â��āu�����P�����ƂȂ̂��v�����ɂ߂��ړI�����邱�Ƃ��ł���\�́B�B���s�\�ȖړI�⋭���I�ȖړI�A���K�I�ȖړI�ł͂Ȃ��A���◝�z�̎����Ɍ������ړI�A��z����Nj�����ړI�ł��邱�ƁB�A���ς���\�́F����������̂܂܂Ɋς�\�́B�l�ɂ́A���������̂������Ȃ��A�������Ȃ����̂͌��Ȃ��A�Ƃ����X�������邪�A���������X�������邱�Ƃ�m���������ŁA����ς�v�����݂�r�����āA�܊�����g���Ȃ���A1���N���Ȃ�����E�����E����������̂܂܂Ɋς邱�ƁB�B�������\�́F�V���Ȓm��n�������邱�ƁB�K�ޓK���̐l�ނ��^�C�����[�Ɍ����o���z�u���A�����E���U�E���̏�����邱�ƁB�C�{�����\�́F�N���]����p�Y����̗���ɉ����āA���҂̋L���Ɏc��A���҂̍s����ϗe������悤�ȃX�g�[���[����邱�ƁB���Ƃ���g���b�N���g���āA�r�W������R���Z�v�g�𑼎҂̃R���e�N�X�g�ɍ����悤�ɓ`����\�́B�D�e���͂��g��������\�́F�r�W������R���Z�v�g���������邽�߂ɁA���҂ւ̉e���͂��g�������đ��҂����\�́B�╶���ɍ��킹�āA�n�[�h�ȗ́i�O�I�ȓ��@�ő��҂��]�킹��́j�A�\�t�g�ȗ́i���I�ȓ��@�ő��҂��]�킹��́j�ƃX�}�[�g�ȗ́i�]���Ă���Ƃ����ӎ������������ɏ]�킹��́j���g�������邱�ƁB�E�g�D����\�́F�@����D�̔\�͂�`�����A�l�����琬����\�́B ������l�������̔\�͂����悤�ɂ��āA���ׂẴ��x���Ɏ������U���Ă���t���N�^���^�i�����`�j�̑g�D�����邱�ƁB

�r�c�f���̊�b
�@�����\�Ȕ��W�ɊS��������҂���������B
�@�����́A���{�ɂ�����o�c�N�w�̑�\��Ƃ��āA�ߍ]���l�́u�O���悵�v��������B�u�����肪�������A����肪��������Ƃ����̂́A�����Ƃ��ē��R�̂��ƁB���ԁi�Љ�j�ɖ����A�܂�A�v���ł��Ă����悢�����v�Ƃ����A����̗��v�݂̂�Nj����邱�Ƃ��悵�Ƃ����A�Љ�̍K�����肤�u�O���悵�v�̐��_�́A�����̊�ƂɂƂ��Čo�c���O�̍����ɂȂ��Ă���Ƃ����̂��B�����āA�u�O���悵�v�̗��O�����ԓI�ɂ��A��ԓI�ɂ��L�������̂Ƃ��Ăr�c�f�����Ƃ炦�A���Ƃ��A�����Ɣ����肾���ł͂Ȃ��T�v���C�`�F�[���S�̂��������邱�Ƃ�A�n�����S�́A����ɂ́A�����̎Љ��S����������̖����܂ł�����ɓ����悤����B
�@�]�҂́A�A�E��N�Ƃɂ����āA����̐E�Ƃ��A�l�ނ�n���̑����ɂ��v������Ƃ������̂���E�Ɗς����Ă��҂́A�ꕔ�̃G���[�g�Ɍ����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜����B�i���̊g��ƕs���̉��s�̂Ȃ��A�����̎�҂́A�d���ɖ������Ă��ɂ���悤�Ɏv����B�����ŒE�������҂ɑ��ẮA�l���Љ�ł́A�u��������Ȍ���Ȃ̂����玩�ȐӔC�v�ƒf������B�����ł́A�u�N��l���c���Ȃ��v�Ƃ������O�͗��z�_�ɂ����Ȃ��Ƃ����悤�B��҂�����̑��݂̎Љ�I�Ӌ`���m�F���A����Ɋ�Â������Ȍ��肪�ł���悤�ȎЉ�I����̊l�����d���������B
�@2015�N9���Ƀj���[���[�N�̍��A�{���ɂ����āA�u���A�����\�ȊJ���T�~�b�g�v���J�Â���A�u��X�̐��E��ϊv����F�����\�ȊJ���̂��߂�2030�A�W�F���_�v���̑����ꂽ�B���̖ڕW��17�̃S�[����169�̃^�[�Q�b�g����Ȃ�A�����\�ȊJ���ڕW�i�r�c�f���j�ł���B�r�c�f���́u�N��l���c���Ȃ��v�Ƃ������O�̂��ƁA���E�̉ۑ��ԗ��I�ɂƂ肠���Ă���B
�@�����́A����ɂ��āA�u�Ƃ�킯��ƂŁA�o�c�̒����ɐ����邱�Ƃ��z�肳��Ă���v�Ƃ��A�Љ�I�ӔC�Ƃ��Ă̎�g�݂݂̂Ȃ炸�A�Љ�ۑ�����v���ƂƂ��Ď�g�ށu�{�Ɖ��v�����҂���Ă���Ƃ��Ă���B�����āA���N�E���E�G�l���M�[�E�܂��Â���E���������E�W�F���_�[���́u17�̃S�[���v�Ɋւ��āA�v��ŏI�N2030�N�̖]�܂��������͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�Ȃ��r�c�f���͐V���Ƃ̊J���ɖ𗧂̂��A�V���ȍL��E�R�~���j�P�[�V�����Ƃ��Ăr�c�f�����ǂ����p���ׂ����Ȃǂɂ��ďq�ׂĂ���B
�@�����́A���{�ɂ�����o�c�N�w�̑�\��Ƃ��āA�ߍ]���l�́u�O���悵�v��������B�u�����肪�������A����肪��������Ƃ����̂́A�����Ƃ��ē��R�̂��ƁB���ԁi�Љ�j�ɖ����A�܂�A�v���ł��Ă����悢�����v�Ƃ����A����̗��v�݂̂�Nj����邱�Ƃ��悵�Ƃ����A�Љ�̍K�����肤�u�O���悵�v�̐��_�́A�����̊�ƂɂƂ��Čo�c���O�̍����ɂȂ��Ă���Ƃ����̂��B�����āA�u�O���悵�v�̗��O�����ԓI�ɂ��A��ԓI�ɂ��L�������̂Ƃ��Ăr�c�f�����Ƃ炦�A���Ƃ��A�����Ɣ����肾���ł͂Ȃ��T�v���C�`�F�[���S�̂��������邱�Ƃ�A�n�����S�́A����ɂ́A�����̎Љ��S����������̖����܂ł�����ɓ����悤����B
�@�����Łu�V���Ƃ̊J���v�Ƃ́A�C��ϓ��A���N�A����A�H���ȂǁA�n���K�͂ōL�͂ȎЉ�ۑ�ɑ��A���Ђ̌o�c���������p������������l���邱�ƂŁA�V���Ȏ��Ƃ̍\�z�ɖ𗧂Ƃ������ƁA�u��Ɖ��l�̌���v�Ƃ́A���Z�Ⓤ���̑��ʂł��A��Ƃ�����Љ�̉ۑ�ɂǂ��Ή����Ă��邩���d�������悤�ɂȂ��Ă���A�r�c�f���Ɏ��g�ނ��ƂŁA��Ɖ��l�̌���Ɍ��т��Ƃ������ƁA�u�X�e�[�N�z���_�[�Ƃ̊W�����v�Ƃ́A�r�c�f���ƌo�c��̗D��ۑ���������Ƃ́A�ڋq�E�]�ƈ��E���̑��X�e�[�N�z���_�[�Ƃ̋����������ł���Ƃ������Ƃ��Ɛ��������B
�@�����́A��Ƃ̌��I���������炩��搂��B�s���Љ�Ƃ��Ă��A�Љ�ۑ�̉�����A���ǂ��Љ�̍\�z�͌��I�Z�N�^�[�̖����ł���Ƃ�������ς��̂āA�u�l�ƎЉ�����{��
��x���Ă����Ƃ�����v�Ƃ����ϓ_����L���p�[�g�i�[�V�b�v��g�ނ̂�����ƌ����̂ł���B
�@�����āA�r�c�fs�̂悤�Ȓ����I�Ȏ��g�݂ł́A�������S����҂Ɋ��҂��W�܂�₷���Ƃ��A�����̂����҂ɑ��āA�V�j�A�̎Љ��ς��������̌������悤�咣����B�ꌩ�B����������ȖڕW�ł����������ɎЉ�I�ȓw�͂��p�������悤�ɂ���ɂ́A�������������̌��Ɗ�]��������ɂ�����Ɠ`����̂������厖�ł���Ƃ����̂��B�����āA�����̍K���x���x���鉽���ǂ��q�d��x��Љ���A���̎������͎c���K�v������̂ł͂Ȃ����Ƒi����B
��ҕ����������͎�҂̕����E�L�����A�E�x������Ƃ��錤�����ł��B